【プロローグ】
「なんだろう、ここ……」
はじめて来たのに、すごく懐かしい……。
「どうして……」
ふと足が向いた、焼け落ちたような家の残骸しかない広い空き地で、わけもなく泣きたくなりぺたりと地面に座り込んでいたら。
足元をかすめるように進んでいる蛇の姿にぎょっとして、ついで、すぐそばで聞こえた、犬の鳴き声。
そして――
「我が探偵社へようこそ!」
空から降ってきたフレーズに、こみ上げていた涙がとまった。
そこには、屋敷の残骸の上に広がるには少々不似合いな青い空をバックに、金色の髪をした男の人が微笑んでいた。空よりも青い目が綺麗だった。
わけもなく――懐かしい、甘い感触が、頭上に広がる青空みたいに胸の中にどこまでも広がっていくのを感じた。
「あなた……誰ですか?」
ひどくまっとうな質問を向けたら、ひどく複雑な表情になった顔が印象的だった。
|
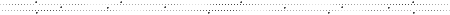 |
【 一 】
「良かった、生きてた!」
ぼろぼろの屋根につぎはぎだらけの壁。補修した床に、出処はあまり聞きたくない気配がぷんぷんする椅子や机。
狭い小屋にぎゅうぎゅうと押し込めたそれらをがたがたと揺らせるほどに明るい声が、そのぼろ小屋に響いた。ひどい夏の暑さの中、一服の清涼剤と表現できるほどにまぶしい白いワンピースを着た、髪の長い女の子だった。
年の頃は十七・八だろうか。長い髪を緩めのおさげにし、それがまた良く似合っていた。
夏の陽射しに容赦なく照らされてむわりとこもった空気が、彼女が開け放した引き戸から吹き込んださわやかな風によって窓から外へと押し出されるのが目に見えるようだ。
「やぁまゆら、いらっしゃい」
彼女から『生きてた』と安堵されたぼろ小屋の住人は、彼女の心配などちらともわかっていない顔で気軽に声をかける。
彼女よりかはあきらかに年上だとはわかるが、やや年齢不詳の若い男は、手にしていた分厚い書類を机の脇へと押しやった。その所作は、ぼろぼろの上にいくつ『ぼろ』とつけても足りないほどにぼろぼろな掘っ立て小屋には似つかわしくない、どこかしら優雅ささえ醸し出したものだった。見た目も、金色の髪に青い目で、ぼろ小屋とは釣り合いの取れない見てくれだったが、彼は現状に疑問すら抱いていないようであった。
と言っても、元からがぼろ小屋であるので机もそんなにひどくなく、書類は分厚い辞書や資料の上に投げ出されただけにすぎなかった。
まゆらはサンダルの足を繰り出して部屋の中へと入り、お土産だとコンビニエンス・ストアのビニール袋を差し出した。
「アイス買ってきたの。一緒に食べよ。ロキさんはなにがいいかなって考えたんだけど、こっちでいい?」
まゆらが差し出したのは、コーヒークリームのカップだった。袋の中には、ストロベリーのカップが残っていた。
……アイスの中ではコーヒークリームが好きだって覚えていたんだ。
ロキはそんな『謎の言葉』を飲み込んで、ただ一言『ありがとう』とカップを受け取った。
「ところで『生きてた』って、ちょっとひどくない?」
涼をとる為に窓とも言えない窓は開け放していたけれど、体は蒸し暑い室温に慣れていただけらしい。アイスは口内でじわりと溶けて、その温度差に身震いまでしそうだ。
まゆらはストロベリーのアイスにスプーンを突っ込みながら、
「だって、この中で一番体力なさそうなんだもの、あなた」
最近は過ごしやすい日が続いてたから心配してなかったけど、今日は反動で恐ろしく暑く感じるからね。
「真っ先に倒れてそう。細いし、色白いし」
細くて白いのはキミもだろう、とロキは苦笑した。
さすがに細くても白くても、少々の暑さで倒れるつもりはないのだけれど、彼女にはそう見えていたらしい。
まゆらは小さくすくったピンク色の氷菓を口に運びつつ、ほてほてとロキの近くに置いてある水槽へと歩み寄る。
「良かった、キミも生きてた」
水槽の中には、熱帯魚でもカエルでもハムスターでもコオロギでもカブトムシでもなく、蛇が一匹入っていた。
若い女の子が覗いてにこにこするような生き物ではないはずだが、まゆらはもうひとすくいアイスを口に運びながらにこにこと蛇を眺めている。
水槽の中の蛇は尻尾から顎の下までぴっとりと地面につけて目を閉じていたが、まゆらの視線を感じたのか、少しだけ頭をあげて挨拶でもするかのように首を振って見せた。
全身にびっしりと生え揃った小さな鱗は光をはじいて七色に輝き、美しいと言えなくもない。爬虫類独特な目も不思議な虹彩で、愛嬌があった。
「不思議よねぇ。わたし、蛇は大っきらいなんだけど、どうしてだかキミは怖くないよ」
人差し指でつんとガラスをつつくと、もう興味をなくしたのか、蛇は再び頭を下げ、目を閉じてしまった。
「まゆらは、蛇、苦手なんだ?」
「もぉうすっごく苦手。本当なら、蛇がいるところにいたくないけど……どうしてだかこの子は大丈夫」
どうしてなのかなぁ? 蛇なのに、なんだか目が優しいから、この子は好きなの。
まゆらは不思議そうに笑いながら、今度はほてほてと反対側へと歩み寄る。
「わんこも元気ね」
床材が剥き出しの日陰に腹をつけて寝そべり、舌を出しているのは黒い犬だった。真っ黒であるだけに熱吸収率がいいのか、犬は夏の間中日陰を追いかけて生活しているようなものであった。
近寄ってきたまゆらに蛇と同じく頭をもたげたが、こちらは挨拶のつもりではないらしい。
まゆらが手にしたストロベリーのカップにぐいっと顔を寄せ、いきなりずぶりとアイスに鼻先を突っ込んだ。
「あぁーっ! わたしのアイスーっ」
あっと言う間に半分平らげられてしまってはもうどうしようもない。
一息に半分食べ終わった後、半死人状態ででろんと床に這いつくばってしまった犬を見るに、まゆらは
「もういいよぅ。全部食べても」
そう言うしかできない。
まゆらと犬のやりとりを眺めて、ロキは思わず吹き出していた。
「犬は苦手じゃないんだ?」
「犬は嫌いじゃないけど、アイス食べちゃうわんこは嫌いかも」
残りのアイスを、今度はぺろぺろと大切そうに舐めていた犬は『がびーん』とばかりに凍りついた。
こんな反応を見るたびに『実はこのわんこ、日本語がわかるのかも』と思わずにいられない。『人語を解する犬』ってテレビに売り出したら一躍有名になるかも! とひそかに考えているまゆらであった。
「でも、ここ、こんなに暑いんだもの。気持ちはわかるわ。ねぇロキさん、ホントに大丈夫?」
涼しげな白いワンピースのまゆらも、すでに薄っすらと汗ばんでいた。
「うーん、原稿料が入ったら扇風機でも買わないといけないぁとは考えているけれど……」
空になったアイスのカップに向けて、律儀に手をあわせて『ご馳走様でした』と頭を下げるロキの仕草にまゆらはあははと声をあげて笑ったが、百パーセントの明るい声にはならなかった。
「せっかく『探偵社』って看板掲げてるのに、ロキさんってば最近もっぱら翻訳家だね」
まゆらはちらりと、玄関とも言えない出入り口へと視線をやった。そこには木板の切れ端に墨で書いた『燕雀探偵社』の表札があるのだ。
『お気軽にどうぞ』と語尾にハートマークまで描いてあるが、ここを訪れる者なんぞ近所の暇な老人か詮索好きな主婦くらい。『お気軽にどうぞ』も意味合いが違うんだけどなぁとまゆらは考えずにはいられなかった。
それよりもなによりも、探偵が探偵らしい仕事ができないこの現状が、探偵好きなまゆらにとってはご不満であった。
「翻訳って地道な仕事のわりに賃金安いんだ。でも、さすがに事件も依頼もないんじゃぁ『探偵』や『依頼』にこだわっているわけにはいかないし。背に腹はかえられないってね」
他の仕事があるだけありがたい、とロキは苦笑した。本当、なにがどうなって書類や本の翻訳の仕事を引き受けるはめになったのやら。最近はもっぱらそちらが主な収入源だし。
と、そこまで考えて、探偵社の実入りの少なさにまゆらが知人に八方手をつくし、翻訳の仕事を紹介してくれたのだと思い出す。
『ロキさんだったら翻訳できるんじゃないかって思っちゃったんだけど、わたし、確かめもせずに仕事もらってきちゃったのよね。大丈夫だったかな?』
仕事を持ってきてから慌てて確認をしたまゆらには、自分がなにを根拠にそう思ったのかわかるはずもない。
それは、彼女の中の、記憶の残滓が成したこと。自覚も認識もしていない彼女には、理由は一生わからないだろう。
彼女がなにを不思議がっているのか知りつつも答えを返せないばかりか、なにからなにまで彼女にはお世話になっているのはさすがのロキにも心苦しいものがあったが、彼女は苦労をも楽しそうにしているだけだった。
『ロキさんだったらモデルも問題ない気がするけれど……戸口で毎回頭打ってたり、道でつんのめってるようじゃぁねぇ』
いつぞや、そんなことも気楽に言っていたけれど、まゆらはやはり『探偵』にこだわっているようであった。
「そうなんだよねぇ。あーあ、なにか不思議ミステリーとか怪盗事件とか起きないかなぁ。そうしたらわたしとロキさんがじゃじゃんっと登場、ぱぱっと解決してみせるのに」
「あると言えば、二丁目の有木澤さんちのわんこが三日前の雷に驚いて脱走、行方不明」
もうそんな犬猫探しはいやーっ。
まゆらは小さく叫んだが、叫んだ勢いでしょぼしょぼとへたりこみ、
「ロキさん、そのわんこの写真見せて。わたしも探しとくから」
腕だけ伸ばしてロキに写真と依頼書を催促する。
「あ、ビーグルだ」
愛嬌のある垂れ耳のわんこがこちらに向けて笑っている。
犬種を覚え始めてきた自分がちょっとイヤ、と感じつつもすっかりと犬猫探しのエキスパートになりつつあるまゆらであった。
|
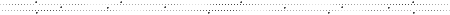 |
【 二 】
「おー、ホントにこんなところに人が棲息してる!」
まゆらが開け放したままになっていた立て付けの悪い引き戸からひょいと顔を覗かせ、ぼろ小屋の住人本人に向けるには非常に不謹慎な台詞を誰かが吐いた。
声は非常に若く、実際に若い男だった。年頃はまゆらと同じくらいだろうか、涼しげなTシャツに色の抜けたジーンズ姿で遠慮なく掘っ立て小屋を覗いている。
顔立ちはなかなかに整っていたが、どことなく優等生タイプとは正反対の立場を連想させた。ある意味抜け目ない性格を強くあらわした顔立ちだ。そして彼は実際、優等生とはほど遠いタイプで、抜け目ない性格であった。
「光太郎君!」
「……大堂寺か? なんだ、ここ、あんたんちか」
違う違う、とまゆらは手を振った。
「ここはね、このロキさんの探偵社なの。そうだ、ロキさんははじめてよね。こちら、垣ノ内光太郎君。学校は違うけど、同じ年なの」
ども、と軽く頭を下げた光太郎に向けて同じく会釈を返しながら、ロキは複雑な心境だった。
はじめまして、ではないのだけれども……『燕雀探偵社の少年探偵ロキ』として出会った人物と会う瞬間は、微妙に、心構えが必要だ。少しばかり寂しい気分になるから。
相手はおのれを知らなくても、こちらは相手を知っているのに。
その温度差は寂しさにすりかわる。彼らが悪いわけではないと知りつつも、別者扱いされた心は、寂しい。
「それにしても光太郎君、どうしたの? もしかして依頼?!」
まゆらは両手を胸元でがっしとにぎりしめ、目をキラキラさせ、今にも光太郎に詰め寄らんばかりだ。
「あんたなぁ、ほんっとーにこれさえなきゃぁ……って、そうじゃなくて、まぁ、依頼と言えば依頼なんだけど」
やた! 依頼だ依頼!
まゆらは両手をあげてバンザーイと喜びながらくるくるとまわっていたが、突然我に返って
「それ、犬猫探しってオチじゃないよね??」
「あんた喜ばすの癪だけど、結構まともな怪奇現象だったりして……なぁ」
光太郎は言葉を濁し後ろ頭をかきながら、見た目ぼろぼろで内装もぼろぼろな探偵社と、その中において絶好調で不釣合いな『探偵』を見比べ『大丈夫か?』と小さく呟いた。胡散臭さが大爆発の取り合わせだ。
「大丈夫もなにも大丈夫だよ! なにせロキさんはすっごい探偵なんだから!」
って言っても、わたしがここに来てからの事件って、犬猫か迷子探し程度なんだけど、とまゆらはぺろりとしゃべってしまい、光太郎は非常に『信ずるに足りないモノ』を見る目でまゆらを眺めた。
「いや、まぁ、なんだかオレもわからないんだけど……ここに来たら事件は解決するんじゃないかって気がしてやって来たくらいだから今更本当に探偵社があって依頼しないってのは変だし、いいんだけど」
あーもう、この話聞いてから頭ん中整理できなくて気持ちわりぃなッ! 光太郎は短く吐き捨て、頭をがしがしとかいた。
よくわからないけれど、直感に従ってここまできたら、ぼろぼろではあっても『探偵社』があった。それがまた驚きであるのに、なぜか理由もなく『これで大丈夫』と考えている自分の気持ちが一番気持ち悪い。
「えっと、コータロークン? 怪奇現象の事件ってナニ?」
こーたろーくん?? なんかそれも気持ち悪い。
光太郎はロキの呼びかけを舌の上で転がして、その違和感に顔をしかめた。
ここは自分とはとことん相性が悪いのではないだろうか、とありありと嫌悪の表情を浮かべた光太郎に、
「……光ちゃん?」
ロキが慎重に言い直したのだと光太郎もまゆらも気がつかず、ただ、部屋の隅でアイスを食べ終えた犬だけがぴくりと耳をそばだててロキの顔を見上げた。
「あぁ、まぁ、事件って言っても、別に人が死んだとかそんな大げさじゃないんだけど……。親父が経営しているスポーツ・ジムの水が、急に消えたんだ」
「水が消えた?」
最新鋭の運動機器や、エアロビクスからヨガなどの講座を各種備えた屋内型スポーツ・ジムの二十五メートルプールの水が、昨日の閉業直後にいきなり消えたと言うのだ。
「スタッフ連中の話からすると、閉業作業でプールから全員の目が離れたのはおおよそ十分。でもそれだけなら別になんらかの事故で排水しちまったってことで、整備室の修繕とかスタッフの管理体制の見直しで話は終わるんだ。まぁ排水時間の関係を考えれば不自然極まりないけど、話はこれだけじゃないってわけで」
予定していないプールの排水に驚いたスタッフが大慌てで予定表を確認しに出た五分の間に、プールは再び満々と水を湛えていたらしい。
「な、怪奇現象だろ? 排水も時間無視だし、貯水はそれを上回っている。気持ち悪がったスタッフが言いふらす前に原因を突き止めようってことになったんだ」
でもそのあたり面倒くさがりの親父はオレに仕事を押し付け……と説明をしていた途中で、光太郎はなにかに気がついたらしい。
「そう言えば大堂寺、あんたとオレって、なにがきっかけで知り合ったんだっけ? 部活関係ってのもなさそうだし……そもそもオレ、帰宅部」
「んー。さっきっから考えてるんだけどぉ、思い出せないんだよねぇ。誰かの紹介かなぁ?」
「学校も近くないしな。ゲーセンか?」
わたし、あんまりゲームセンター行かないし……まゆらと光太郎はうんうんとうなっていたけれど。
「ま、いいや、どうでも。ね、ロキさん、はじめての探偵らしい依頼だよ! これは受けるっきゃないよ!」
深く考えるなどしないまゆらは、はじめての『探偵らしい依頼』にウキウキと乗り気だ。
「光太郎君ちってお金持ちだから依頼料もがっつりだよ!」
ね、依頼料でるよね! まゆらはしっかりと光太郎に詰め寄った。どうやら、超がつくほどに貧乏な燕雀探偵社の家計具合も心配されているらしい。
「んー。そりゃぁ面白そうな事件だから受けたいけれど」
光太郎に提示された手付けの金額も、扇風機を購入しないと茹で死にそうなぼろ小屋の住人であるのでたいそう魅力的だから受ける気ではいるけれど……。
「とりあえず、現場を見せてくれる?」
話を聞くだけでも不思議な現象に、もはや『不思議の存在』ではないおのれにどれだけのことができるのか――ロキにはわからなかった。
|
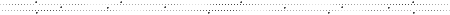 |
【 三 】
各種産業に手広く進出している光太郎の父親が経営しているその会員制スポーツ・ジムは、街の中央部から十分ほど車で西に走らせた場所にあった。
広く取られた敷地には三十台ほどの駐車スペースもとられ、エントランスもなかなか立派であった。
「ロキさん、本当にバスとか苦手よねぇ」
至れり尽くせりの会員制スポーツ・ジムの駅からの送迎バスは、臨時休業となった本日もかろうじて動いていた。
座席は広くとられていて、クッションもほど良い感じの、なかなかに居心地の良いバスだ。なにごとにも経費を削らない垣ノ内グループらしい。
「う〜ん、だいぶ慣れてきたけど、やっぱりキライ」
居心地の良いバスであったはずなのに、バスからよれよれと降りてきたロキは今にも倒れそうである。
「バスと同じマークだね」
まゆらが指差したのは、建物の上部に描かれた、円形に飛び込む青いイルカ。ジムのシンボル・マークだ。
建物自体は、白と薄いグレーの横ストライプの外壁をした箱型の二階建て。変哲もないと言えば変哲もない建物だ。
更衣室や多目的スタジオは二階に、プールや運動機器は一階に住み分けられているらしい。
水の怪異があった為もあり、出入り口は閉じられ『本日、点検日につき臨時休業』の札が垂れ下がっていたが、光太郎が連絡していたのだろう、スタッフは問題なく三人を招き入れた。そのまま、一般的な、一度二階に戻り更衣室から一階に向かうルートではなく、スタッフ専用ルートから直接プールへと向かった。
「わぁ、明るくてひろいー」
高くとられた天井、大きくとられた窓。夏の陽射しが、照明を落としているプールをやわらかく照らしていた。もちろん、内側から外はよく見えるが、外からの視界は完全シャットアウトの特殊ガラスを透過した光であるので、どことなく非現実めいた光だった。
しんと静まり返った水面や空間に響き渡るまゆらの声は、どこかしらまろやかに感じられ、水の中へと消えて行く。
「それにしても、プールの水って毎日入れ替えるんじゃないんだね」
まゆらは広いプールの大きさを測ろうとでもしているのか、両腕を大きく伸ばした。そんなことをしたくらいで、大きさが測れるはずもない。
「でっかい濾過装置で濾過して、あとは塩素で消毒殺菌がセオリーじゃないか? 源泉掛け流しじゃない温泉も濾過装置があるし」
「銭湯は毎日入れ替えるよね。昔のホームドラマの温泉モノで毎日掃除するシーンあるもの」
プールと温泉の舞台裏ってあんまり聞きたくないなぁ。
まゆらは耳をふさいでこれ以上は聞かないフリをした。
と、視線の先に隅の棚に整頓された青いビート板を見つけたまゆらが、
「ビート板! なつかし〜〜!」
本来の目的をすっかりと忘れ去り無邪気に駆け寄っていくのを好き勝手にさせて、ロキはぐるりとプールの空間を見上げた。
等間隔に設置された照明。夏のキャンペーンの広告。どこにも不審なものは見受けられなかった。
プールに目をやれば、六レーンに区切られており、二階からおりてくる形になる通路側には飛び込み台が設置してある。その奥には、会員制のジムらしく、体をあたためる風呂場のような設備もあった。タイム表示なのか、小学一先生の教材を巨大化させたような時計もあった。
プールの底は青い塗装。五メートルごとに引かれた白いライン。
プールには、一度消え、再び短時間であらわれた、プール一杯分の水。
かすかに揺れる水が、夏の光を床に描いて遊んでいる。
「この水は現状のまま? 塩素とかは入れていないんだ?」
ロキは片膝をつき、右手を差し入れて水をすくいとる。さらさらと手の平からこぼれる水の感触は、広いとは言え閉めきられ湿気に富んだ室内ではことさらに気持ちが良かった。
「あ、おい、それはないだろ?」
光太郎が慌てるのも気にも留めず、ロキはすくいあげた水を口に含む。甘い。塩素の鼻につく匂いもしない真水。
いや、真水と言うには、まだ甘い。甘露水とでも呼ぶのがふさわしい、水本来の甘味がある。雪山近くの春の湧き水か。森の土に濾過された清水か。なぜかしら懐かしさを呼び起こす甘さだった。
「って、オイ、大堂寺?!」
先と同じに光太郎が慌てているが含まれている名前にふと視線を転じると、ロキの真似をしているのか、まゆらまでもがプールの水を飲んでいた。
「ちょっと、まゆら?!」
さすがに自分は良くてもまゆらが飲むには問題がある。
ロキも慌てて声をあげるが、
「わ、甘い。おいしい」
……彼女はまったく自分の行動がどれだけ男どもを慌てさせているのかわかっていないらしい。
「ホント、あれさえなきゃぁな」
光太郎が無感情で呟いた。本当に、とロキも同意したくなってしまった。
男どもに生ぬるい連帯感を抱かせたとも気付いていないまゆらは、指先で水を弾いては『えいっえいっ』とこちら側に水の橋をつくろうと頑張っている。彼女の目的はすっかりと『水遊び』にシフトしてしまったようだ。
「ところで探偵、こんなんでなにかわかるか? 一応現状維持はしておいたけど、なにせなにがかわったって『水』が変わっただけだしな」
「うーん、さすがにこれだけじゃぁ手の出しようもない。おまけに、排水も貯水も、どれだけの量をいっぺんに処理できるのかはわからないけど、五分や十分じゃ無理だってのは確実だねぇ」
短時間で消え、短時間で元に戻ったプール。誰かの作為にしても、こんなことをしてなんの意味があるのだろうか。
しかも、水は水道水とは思えないほどに甘い。
プールの水は別の場所から取水しているのかと確認してみれば、変哲もない水を使っているとの回答がスタッフからも得られていた。
「それよりも、こんな『一度』の現象だけで気持ち悪がっているって、そっちの方が気になるな。なにか情報、あるんじゃない?」
おぉ? 初対面にしては性格読んでるねぇ。
光太郎はにやりと笑い、ポケットから一枚の紙片を取り出した。
「これに似た現象がわかってるだけでも三件起きてる。近くの小学校二件と高校のプール。裏は取れてないけど、この三件に関しては二日前かららしい。でもって、スタッフの子供が通っている小学校ってのがその内の一件で、気持ち悪がられてるってワケ」
『なにせ、昨日の今日だからこれが精一杯』と光太郎はぼやくが、ロキからすれば『さすが光太郎』だ。無駄に日々遊びまわっているわけじゃないらしい。たいした情報通である。
「これから行くのか、探偵?」
ロキはプールサイドの向こう側のまゆらと紙片を眺め、首をふって否定した。
「いいや、明日にする」
なにせ今日は夏祭りに誘われているんで、と視線だけで示した反対側のまゆらは、壁にかけられた丸い時計が刻んだ時刻に気付いたのか蒼白になっている。
「二週間前からしつこく誘われてたから、そろそろタイムリミット、かな」
なにせ、女の子の仕度には時間がかかるから。
まゆらはプールサイドの向こう側から『はやく帰ろう!』と大きく手をふった。ぴょこぴょこと跳ね飛んで、非常に危なっかしい。
「へぇ、怪奇現象の方が絶対優先順位高いと思ってたのに、イガイ〜」
「まぁ、そのあたり彼女も女の子らしくなったのかなぁ、と」
ロキは微妙な声色で賛同し、光太郎は意味ありげな視線をちらりと投げかけただけであった。
|
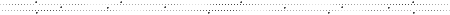 |
【 四 】
二十四時間明かりの絶えない昨今であるので、午後七時前であっても暗がりに困ることはない。夏真っ盛りであるので尚更だ。
ロキとまゆらは、燕雀探偵社から程近い神社の境内で行われている夏祭りへとやって来ていた。
緩やかな坂をのぼった先にある神社は境内こそ広くはないが、坂の長さが幸いして昔から市が立っていたらしい。夏祭りはその名残りであるようだ。
空を見上げれば薄い紫や夕焼けの朱が入り混じる、オーロラに似た空。
街の明かりや薄い夜の色にまぎれて星はまだ見えないが、かわりに、屋台や木々に通された小さな電球がほんわりと空をオレンジに染めていた。
昔なら率先して赴こうとはしなかった人の群れの中を、ロキはゆっくりとした歩幅で歩く。昔とは違い人込みに埋もれるどころか背が高いので、大きくたわんだ飾り付けの電球に髪先をひっかけるありさまだ。
「まゆらのところは夏祭りとか、市は立たないの?」
「うちの神社は階段が長くて急だから、そのあたりのことには不向きらしいの」
クリーム地に古典模様の大輪の花、涼しげな浅葱色の帯に、最近のお洒落を取り入れたビーズの鎖を下げた浴衣姿のまゆらがからころと小さく下駄を鳴らしながら歩いているさまは、実家が神社で巫女装束も着慣れているからか、とても良く似合っていた。
きっちりとあわせた胸元には清潔さが、結い上げた髪から覗く白いうなじからは年頃の色香が醸し出されていた。
彼女が歩くたび、髪にさしたかんざしの先に飾られたガラス細工の蝶がゆらゆらと揺れている。
「フェンリル、先に行っちゃダメだよ」
ふたりの足元には、夜に溶け込むほどに黒い犬がほてほてと歩いていた。夕方になり涼しくなってきたからか、昼間とは違いやたらと元気だ。
人込みを歩くマナーとして首輪とリードをつけてはいたが、フェンリルと呼んだ犬のリードを持つロキは犬を制御するつもりは毛頭ないのか、他人に迷惑をかけない範囲であれば好き勝手に歩かせていた。普通なら駄目飼い主決定の流儀であるが、フェンリルはそのあたりはきちんとわきまえていて、無闇に人の足元を歩き回ったりかぎまわったりの粗相はしなかった。林檎飴の甘い匂いに鼻をひくひくさせたり、子供向けのお面屋の前でぎょっとした顔をしているのを見るのは実は楽しい。
そのフェンリルが食べ物よりも強く興味を持ったのは、くるくると微風にまわるかざぐるま。屋台の前で動かなくなり、口をぽかんと開けてかざぐるまがまわるのにあわせて目を動かしている。まるで、人間の子供のようだった。
「わんこ、かざぐるま好きなの?」
もちろんフェンリルは答えられるはずもなく、ただぐるぐると回り続ける二色のかざぐるまを目で追って、くらりとよろけた。
「目をまわすわんこなんてはじめて」
まゆらは明るい声で笑いながら、かざぐるまを一本手にとり代金を屋台の主に差し出した。白と水色の涼しげな二色のかざぐるま。
「わんこにプレゼント。って言っても、首輪にさしたら歩きづらいよねぇ」
じゃぁこうすればいい、とロキは、まゆらの帯の後ろに差し込んだ。
フェンリルはかざぐるまを追って、自然とまゆらの後ろを歩き出す。
「まゆらちゃんとわんこの行進ね」
まゆらが歩くたびにくぅるりとかざぐるまがまわり、それを見上げながらフェンリルがほてほてと歩く。その後ろには、申し訳程度にリードを持つロキが続く。妙な行進だった。
「あ、ほおずき」
次に屋台前で足をとめたのは先頭のまゆらだったので、行進は停止するしかなかった。
射的や金魚すくい、綿菓子やソーダ水売りなどの定番屋台にまぎれてオレンジ色のランプに照らされていたのは、少々珍しいほおずき売り。
ほおずき独特な朱色に色付くのは、本来は九月や十月だ。有名な七月上旬に開催される浅草の『ほおずき市』は、専用に季節をはやめて栽培されたものだ。
目の前に並ぶほおずきも同じ品であるらしかったが、ほおずきの特徴である朱色よりもまだまだ緑味の強い品だった。
背が高いほおずきの葉と同じほどの高さで編まれた竹の持ち手は二本十字に交差され、緑の植物に若い色を添えている。
「ほおずき鳴らす遊びって……ロキさんはしそうにないよねぇ」
どこからどうみても向こう三代日本人の血など混ざっていそうにない端正な面差しをフェンリルのように見上げ、まゆらは吹き出した。『小さな頃のロキ』と言うのも想像しづらいが、彼がほおずきで遊ぶ図はそれ以上だ。
「なにかの小説だったかな? ほおずきの中に蛍を入れて『ほおずき提灯』をつくるってあったの。でも、蛍の季節とほおずきって、時期が違うよねぇ?」
「蛍のかわりに豆電球を入れるのが一般的さね」
顔にも手にもしわがしゃわしゃわと刻まれ、白髪の髪を隠すように手ぬぐいを頬っかむりした老婆が楽しげに教えてくれた。
「じゃぁ、秋になったらやってみます」
まゆらはどの鉢にしようかと、真剣なまなざしで選び始めた。
その真剣な横顔、ロキは不思議な気持ちで眺めていた。
まゆらと言う名の少女を深く知っていた気でいたのは錯覚だろうか。
彼女が『ロキさん』と呼ぶのも。
彼女が黒犬のフェンリルを知らないことや――かつて『闇野さん』と親しく呼んでいた青年のことも蛇のことも忘れ果てている現実も、どこかしらふわふわした夢の中にいるようで。
確かに『起きた事柄』『経験した事柄』が相手の中からすっぽりと抜け落ちている事実を突きつけられるのは、彼女の人生に歪みをつけた背徳感を呼び起こす。そして、彼女がなにかを懐かしむ視線を見せるたび――記憶の残滓よりも儚い感情の波を見せられるたび、背徳感はいや増すのだ。それがいっそ『罪悪感』であれば話がはやいのに、と思わずにいられない。
『偽り』の花言葉を冠されているほおずきを彼女が手にしているのは、『偽り』を積み上げたこの現実世界の象徴みたいで。
――ここにいてもいいのだろうか。
まゆらに明るい声で呼びかけられるたび、ロキは迷うのだ。
偽りの上に偽りを塗り固める為にここにいるわけではないのに――『神の世界』から戻ったおのれはこの上もなく不安定な存在で。
それでも、この時間を『特別』だと感じるのはとめられない。
ロキは、老婆に代金を払うまゆらから視線を外し、空を仰いだ。
夜を世界の端へと追いやるには到底足りない人々が作り出す明かりの中に、自然の力を主張するかのようなひとつの星。
明かりの中にまぎれてしまえば、皆ただの光になれるだろうに、どうしてそんなにも異質感をみずから際立たせようとするのか。
夜には珍しい、鋭い鳥の鳴き声がロキの無意味な思考を断ち切るかのように響き渡り、夕方にしてはまだ生ぬるい風に頬を撫でられ、ロキは目の前の光景へと戻ってきた。
目の前にはみっつの大きな房を持ったほおずきの鉢を嬉しげに掲げたまゆらと、なにやら良くわからないが期待に目をきらきらさせて朱と緑の房を見上げているフェンリルが。
「探偵社に置いてね。見た目だけでも涼しくさせなくちゃ」
さぁ、次はなにがあるかなと先へと進みかけたまゆらの手からやや重たいほおずきの鉢の持ち手をさり気なく交代したロキへと向けて、まゆらが『ありがとう』と笑いかけた。
右手にフェンリルのリードを、左手にほおずきの鉢を提げたロキは、ふわふわと幻想的な祭りの空気にひたされて気がつかない。
人の熱気でむせ返る夏の夜の片隅で、人が寄り付かない神社の裏の小さな池が空っぽになり、再び満々と水を湛えていたことを。
その水が甘く香っていたとしても、誰も気付かない。
鳥はもう一声高く鳴き、夜が忍び寄る東の空へと銀の尾を引き飛んで行った。
|
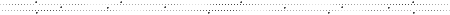 |
【 五 】
「ロキさんロキさん、大ニュース! 昨日の夜、市民プールの水がなくなったんだって! 今度はまだ水が入ってないらしいの!」
朝もはやい時間からにぎやかなまゆらの声がぼろぼろな探偵社に響き渡り、ロキは問答無用で叩き起こされた。
彼女ははやい時点で情報を入手していたのか、手際よくサンドイッチの朝食まで用意しており
「はいっ食べて食べて!」
リズム良くロキを追い立てる。
『食べて食べて!』の前には『着替えて顔洗って!』と矢継ぎ早に指示を出しつつ、本人は窓を開けてフェンリルに朝食を用意し、ほおずきの鉢に水をやり、紅茶をいれ、林檎の皮を剥き林檎をねだるフェンリルに一切れ与え、と狭い探偵社の中をくるくると動き回っていた。
『燕雀探偵社はじまって以来の大事件』に大興奮しているのがありありとわかってなにやら微笑ましく、思わずロキは吹き出した。
「そんなに急がなくても、プールは逃げないだろうに」
「だって、今度は光太郎君のトコじゃなくて、市民プールだもん! すぐに状況がかわっちゃうかもしれないでしょ!」
おや、意外にそのあたりも考えているのか、とロキは少々感心してしまった。伊達に探偵オタクを幼少時からしているわけではないらしい。
そんな騒がしいやり取りの一時間後には、問題の市民プールへとやって来ていた。フェンリルの朝の散歩も兼ねているので、メンバーは昨日の夏祭りと同じ、ロキとまゆらとフェンリルだ。
「蛇がすねないといいけど。いっつもお留守番」
変なところを気にするまゆらであったが、蛇――ヨルムンガンドとの本来の名に戻った彼は、長い体をゆったりとくつろがせて惰眠をむさぼっているに違いないとロキあたりは少々羨ましく考えていた。
そんなことを考えているロキは見た目を裏切らず低血圧気味だった。まゆらにおったてられるように身支度をして現場に赴いたはいいが、頭の半分はサンドイッチをゆっくり消化する暇もなかった為の栄養不足と酸欠と眠気でまともに動いてはいなかった。
それでも、目の前にある『現場』に意識は目覚めるしかない。なぜなら、まゆらが情報をキャッチしてから状況はかわり、市民プールには再び水があふれるほどに湛えられていたからだ。
プールと同じ敷地内にある野球場やテニスコートや公園に植えられた樹に住む蝉が朝から珍しく騒ぐ人間たちに気圧されでもしたのか、しんと黙りこくっているのが不気味だった。
「オイ、誰か水いれたのか? 昨日は確かに空っぽだったのに……」
「排水装置も異常なし。制御室の鍵も主任が持ってるって確認取れた」
「じゃぁ、どうやってカラにできたって言うんだよ」
「田舎とかにある、エンジン付きのホースを突っ込んで水どろぼう? ほら、用水路から水を汲むのに使う……」
「それをやって得なコト、あるか??」
「普通に水道水のが安いって」
ばらばらとばらけたスタッフは様々な意見を出し合い不思議がる。
彼らにまぎれて水を飲んでみたロキは、市民プールもまた一連の怪奇現象に含まれているのだと断定したのだが、問題はそれだけではなかった。
「カラだったっての、警備のおっさんの見間違いじゃないのか? すんごい年寄りのおっさんだったし」
「そーだよなぁ。まったく、人騒がせな……って言っても、コレの前じゃぁ水なんかちっさい問題だよなぁ」
「ホントどうなるんだ、コレ? 休業なんかになったらその間のバイト代どうなるんだよ」
「今から探すの、きついってゼッタイ」
ぶつくさと口々に言い合う、プールのスタッフらしく日に焼けた彼らの晴れやかとは言えない気持ちもわからないでもない。
「けど、なんだって今回はこんな……」
なにせ、まゆらでさえも困惑していたからだ。
プールの水は、情報だけの三件と、昨日出向いて確認したスポーツ・ジムと状況は同じであったが、先の四件とは決定的な違いがあった。
それは、破壊されたプールのフェンスとプールサイド。とてもではないが通常営業できる状態ではなかった。
「これ、どうやったらこんなになるのかな?」
プールそばの道路からプールに向けて、巨大な刀で衝撃を加えでもしたかのような破壊の痕跡。
正方形の石が並べられていたプールサイドはそこだけ粉々になりするどい亀裂を走らせ、フェンスは半壊になり今にも支柱から倒れそうだった。両方とも赤いポールと縄で囲んでいるのが、唯一スタッフがやったことだろう。
破壊痕はプールまで到達してはいなかったが、この新たな現象をどうとらえれば良いのか、今のロキにはわからなかった。
いや……それよりもなによりも、と破壊痕のすぐそばに膝をつき、鋭く走った亀裂を手で確かめながらロキは思考の海に沈みこむ。
この太刀痕は、どこかで――けれど、まさか。
それに、なにやら『彼』らしく『力任せ』の印象も受けるけれど、このあたりは制御が上手く――……
「ロキさん、なにかわかった?」
はっと気がつけば、まゆらが心配そうにロキの顔を覗き込んでいた。
小さな山のふもとに張り付くようにしてつくられた市民プールの周辺は緑が多い。気温があがりかけてはいるが涼しい風がプールサイドに吹き渡る。さわさわと揺れる夏の緑に、まゆらの心配げな声が溶けて行く。
「いや……きっと気のせい」
「?」
なにせ『彼』は――今は遠い世界にいるのだから。こんなとろこでプールなんぞを破壊できるはずがない。
その時、軽やかな電子音が響き渡った。
「ロキさん、電話」
あわあわと後ポケットからロキが取り出したのは、青い携帯電話。まゆらが面白がってつけた河童のストラップが妙に似合っていた。
ロキは携帯電話を取り出したはいいが、電話を手にたっぷり五秒凍りついた。『イヤイヤ』なオーラが全身からにじみ出ているのが目に見えるようだ、とフェンリルはさりげなく目をそらした。
「……ロキさんってほんとーにケータイも苦手なんだ」
はやく出ないと切れちゃうよ? まゆらのまっとうな意見が耳に痛い。
「できれば一生持ち歩きたくないね」
心底から願ってはいるが、今や携帯電話の勢力は公衆電話を駆逐する勢いだ。固定電話を設置するよりも携帯電話の方が料金も安い上に機動性も高いとなれば、好き嫌いは言ってはいられない。なにせ今のご時勢及び探偵業とは、情報とスピードが命なのだから。
しぶしぶこわごわ通話ボタンを押してみれば、それは、二丁目の有木澤家の犬らしき迷い犬が庭にいるのだが……との、張り紙を見た年寄りからの電話だった。もごもごと話すので非常に聞き取りづらい。
なんとか話を聞き取ると、運の良いことに市民プールの近くの住宅地からの電話だった。ただし、探偵社とは反対方向だ。
「まゆら、フェンリルを連れて先に帰っていてくれる? これから暑くなるだろうからヨルムンガンドも心配だし」
「ロキさんってほんとーにこの子たちに優しいねぇ」
……そうかな? とロキが呟く前に、まゆらはフェンリルのリードを受け取ってかろやかな足取りで歩き出し、
「わんこ、公園通って帰ろ」
楽しげに話しかけていた。青い空と白い雲と豊かな緑に映える水色のスカートがなめらかな波をつくって遠ざかっていった。
その足元を彼女の影のようになりほてほてと歩いている黒い犬は、何度か後ろを振り返ったものの、
「水浴びついでに洗ったげようか?」
風呂はともかく、大好きな『水遊び』の単語に尻尾をぶんぶんとさせて跳ねとんでいってしまった。
今日も暑くなりそうだ。ロキはぼんやりと空を仰いだ。
彼女の退場と共に音が戻ってきたかのように蝉が一斉に鳴き始め、ロキに追い討ちをかけるのであった。
市民プールには、隣接して事務所や更衣室がおさめられた四角い一階建ての灰色の建物があった。
その建物の影に隠れるようにして、プールサイドの騒ぎを見守っている人物がふたりいた。
口々に言い合い、好き勝手に動き回るスタッフの騒動を眺めている通りすがりの野次馬かと思われたが、ふたりの視線はフェンスを調べているロキとまゆらにまっすぐ注がれているのだとすぐに知れる。
どちらも無言でロキとまゆらを眺めていたが、その視線はただの『観察人』と言うには視線に鋭いものが混じっていた。
観察人の存在に、ロキが連れた黒い犬は鼻をひくりと動かして勘付いているようであったが、悲しいかな人の言葉をしゃべれない犬にはロキに不審者を知らせるすべがない。じろり、と威嚇の視線をくれるしかできなかった。
観察人はフェンリルの威嚇を合図にしたかのようにふぃと建物の奥へと隠れ、やがて気配もすっかりと消え去るのであった。
|
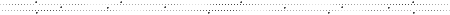 |
【 六 】
夏は暑い。
正午が近くの、太陽が高くのぼる時間であるので尚のこと暑い。
足元の影はどんどんと短く濃くなり、道の先には陽炎さえゆらゆらと立ちのぼるありさまだ。
依頼を受けていた有木澤家の犬らしき情報を受けて出向いた先がとんでもなく入り組んだ住宅地の、おまけに隠れるようにして建っている小さな家でたいそうわかりづらかったことや、ロキが辿り着いた頃には庭にいた犬はとっとと他の場所に移動していたことも体感温度を増す要因になっていた。
もうひとつおまけに、電話をくれた暇そうな、否、実際にたいそう暇らしい九十過ぎの老人にとっつかまり、長々と益体のない話を聞かされた。老人が子供の頃の話から入れ歯の具合から若い時分に付き合った女の数から結婚した奥さんの話やら戦争の話やらと、主に現在の愚痴と男としての自慢話だ。
ある意味、話を聞いてどうしろと愚痴りたくなる話題ばかりではあったが、こちらの言葉を一切聞かない老人相手であるので大人しく聞き役に徹するしかないロキであった。
付き合った女の話など、覚えているだけで三回は聞いた。しかも段々と女の人数が増えていた。もうどうしようもない、とロキはその時点で無理矢理片足を突っ込んだ忘我の境から潔く奈落の底へと落っこちる覚悟を決めたものだ。
ただひとつ得をしたのは、
「あんた、そんなひょろっほそくて、ちゃんとくっとんのか? 奥さんはたべさせとんのか?」
いやボク今は妻帯者じゃないし……扶養家族はいるけど……とのロキの言葉をやはり聞きもせず、犬がいたらしい庭につくっていた家庭菜園からごっそりと夏の恵みをもぎとって押し付けてくれた点だろう。依頼らしい依頼に常にことかく貧困生活の中では、人の情けが身にしみる。
とは言いつつも、両手いっぱいのきゅうりと茄子を抱えて歩くのは一種異様で、一目をはばかりたい姿だ。きゅうりのイガイガは腕に痛かゆいし、茄子のすべすべした皮は妙にくすぐったい。それらの上に乗せられた真っ赤なトマトがふたつ、不安定にゆらゆらと揺れている。狭い庭で作ったのが奇跡に思える、丸々と太った二本のトウモロコシの青々した緑の葉。
暑い中よれよれと夏の恵みを抱えてようやく辿り着いたぼろ小屋は夏の太陽に照らされてしなびて見えたが、それでも大事な我が家だ。もしかしたらまだまゆらも残っているかもしれない。
「ただいま……」
よれよれと引き戸を開けて一歩を踏み込んでみれば、期待していたかろやかな『お帰りなさい』の声のかわりに、男の声がした。
「遅いのだ、ロキ。フレイは待ちくたびれたのだぞぃ」
…………は?
ロキは一瞬、耳に聞こえた男の声とくたびれたソファに座る人物に、思考が完全に停止した。
正確に言えば、目の前にいるのは『人物たち』と複数形になる光景に、だ。
「相変わらずカッコイイのだ、ロキは。だが、この屋敷は前とは雲泥の差だな」
声をかけてきた若い男の隣に座るのは、見間違いやまぼろしや、はたまたおかしな願望でなければ――
「……ヘイムダル?」
そして、みずから名乗ったフレイだ。相も変わらず、季節感を完全無視した暑苦しい盛装姿だ。マントが夏仕様らしく薄手の生地である点に気がついてしまったロキである。
「なんでっ」
さすがに続く言葉を失った。
なんで、どうして、彼らがここに――??
いや、それよりもなによりも、フレイはともかくとして、どうしてヘイムダルは『人間世界での仮の姿』のままなのだ。
微妙に伸ばした前髪で右目を隠した、人相の悪い小学生姿。こちらも相も変わらず『明るさ』やら『ほがらかさ』やら『素直さ』とはとことんと無縁の不景気な顔をしていた。
色々と盛大に問いたいところであるが、あまりにも驚きすぎて声がでない。
もしかしてボク、暑さでやられて、探偵社に帰ってきた夢を見ているだけなのかもしれない……そんな馬鹿な考えさえ脳に湧いてしまう。それだけ探偵社内の光景は予想外だった。
そうだ、ボクは夢を見ているのだ。彼らの存在と今の探偵社。恐ろしいほどに不似合いな夢を……
「あ、ロキさん、お帰りなさい。暑くなってからこっち、探偵社大繁盛だね。フレイさんとヘイムダル君、依頼なんだって!」
麦茶を入れた一リットル入りのガラス容器とグラスをみっつ載せた盆を手に、まゆらがひょこりと顔を出した。どうやら目の前に広がる光景は夢ではなく現実であるらしい。
彼女の手元の状態を見るに、『依頼人』と言う完全無敵の通行手形をぶら下げたふたりを発見して中に招き入れたところであったらしかった。
フェンリルは水浴びをさせてもらえなかったのがご不満なのか、次々に冷たい床を求めて移動しながら珍妙な客人をねめつけている。もぞりもぞりと匍匐前進。とても器用だ、と思わず現実逃避しそうになる姿であった。
「それにしてもわたし、なんだかふたりにはじめて会った気がしないのよね……。どこかでお会いしました?」
不思議そうに小首をかしげたまゆらの手をフレイがいきなりとり、
「はじめて会うのにはじめての気がしないとは! 前世からの運命に導かれたふたりなのかもしれない!」
いざ、手をとりあって赴かん! 愛の惑星へ!
フレイはびしっと空の彼方を指差したが、そこには蛇がとぐろを巻く水槽があるだけだ。指差されたのがご不満なのか、滅多に悪者顔をしないヨルムンガンドが、この時ばかりはシャーと威嚇の音をたて白い牙をむいた。
「蛇と同居はちょっとねぇぇぇ」
まゆらが、苦笑半分、変な人への興味半分の奇妙な顔で笑った。フレイのペースに引きずられることなくぺしりと彼の手を叩いているところなど、彼女も少々成長したのかもしれない。
「面白い人ですねぇ、フレイさんって。ロキさんとどんなご関係ですか? まさか、学校の同級生とか、幼馴染とか」
あ、ちょっとまゆらなに気持ち悪い想像してるんだ。
と思いつつも、ロキは暑さにカラカラの喉を、まゆらから受け取った冷たい麦茶で宥めるのに忙しい。ちなみに麦茶はまゆらが作り置いてくれたもので、渇いた喉にしみわたる美味さと冷たさだ。
「ロキとは『好敵手』と書いて『ライバル』と読む間柄なのだ」
好敵手もライバルも一緒の意味だっ! ロキにかわってフレイに突っ込んだのはヘイムダルだった。でこぼこコンビ漫才は健在であるらしい。
「いや、そーじゃなくてっ。なんでふたりとも、こんなところにいるんだ?!」
グラス一杯の麦茶を飲み干しようやくひと心地ついてから、ロキはやっとその質問を口にできた。
そうだ、なぜ彼らがここにいるのだ。彼らはあの日神界に帰り、壊れた世界に残ったはずなのに――……
偽の『大神』役を演じていた『バルドル』の存在がなくなろうとも他の生命は残った、瓦解した世界に。
「うむ、それがだなぁロキ。大変なことが起きたのだっ!」
フレイは唐突に叫んだ勢いで水槽にびしぃっと向けたままであった指を今度はロキへと差し向け、それからなぜか天井へ、そのまま通り過ぎておのれの背後の壁を指し示した。フレイが振り返ったのではなく、本人はソファの背に沿ってブリッジ状態であった。
バカは放っといて、との言外の言葉がありありと聞こえそうな表情でかわりに続きを語ったのはヘイムダルだった。
だがそれは、フレイのみょうちくりんな動きを再現したくなるほどに変な言葉だった。
「フレイヤとトールが駆け落ちしたんだ」
「………………」
なんですと??
ロキは、頭が暑さにやられて幻聴を聞いているのかと本気で心配になってきた。
それとも、ヘイムダルの笑えない冗談か。冗談にしては笑えなさ過ぎて困ってしまう。これは芸人用語で『すべる』と言うのではなかっただろうか。
言うにことかいてフレイヤとトールが駆け落ち。
天地が壊れても有り得ない。
そこまで考えて『天地は壊れたんだっけ』とおのが所業をふと思い出してしまう。ならば有り得なくもないのだろうか、フレイヤとトールの駆け落ちも。
「フレイはけっして認めないのだ! ロキ、貴様もふたりを見つけるのに協力するのだッ!」
ぐもん! とソファに逆海老反りしていたフレイが復活し、背後を指差していた指をそのままロキへと突きつけた。
ほんの二日前までは冷夏で過ごしやすく、反面仕事は乾され状態であったのに、今は夏真っ盛りの仕事花盛り。少々数日前の光景が懐かしくなってきたロキである。
ロキはどう答えればいいものか言葉を探し、
「……とりあえず、場所、かえよっか?」
どうでもいい提案をするしかできなかった。
|
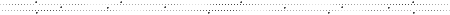 |
【 七 】
燕雀探偵社から一番近い公園には、大きな木が何本も枝を繁らせていた。
木々を縫うように敷かれている石畳の小道の上に、白と緑の光をまだらに投げかけていた。
もちろん樹の足元には、真夏の太陽を遮った、涼しい木陰を提供してくれていた。熱く焼けや空気も幾分かやわらぎ、肺を焼くこともない。
ロキ、フレイ、ヘイムダルの三人は、顔をあわせるでもなくてんでばらばらに木の幹にもたれかかっていた。
蝉は奇妙な三人組に驚いているのか、それともあまりの暑さに元気もないのか、先から沈黙を保っていた。もしかしたら、三人組のただならぬ雰囲気に興味津々に聞き耳を立てているのかもしれない。
「それで? フレイヤとトールの駆け落ちなんて気持ちの悪い冗談引っさげてここに戻ってきた理由を聞かせてくれるかい?」
ロキは腕を組み、ぶすりとした顔で誰にともなく問いかける。
どうにも『フレイヤとトールが駆け落ち云々』のくだりでは顎ががくがくしていけない。そのまま顎が外れてどこかに行ってしまうのではないかと本気で心配になってしまう。
「冗談? フレイは冗談は得意ではないのだぞぃ。真実しか口にしない。いつでも真正直で誠実なのだ」
フレイはこの上もなく真面目な顔で冗談にしか聞こえない台詞を言い切った。元は品のある顔立ちであるので、彼の『普段』を知らない人物が聞けば本気にしそうな台詞群だ。
だが、その『普段』を知っているロキとフレイには通じるはずがなかった。
お前の場合存在自体が冗談だ、と前置きしたヘイムダルが
「フレイヤとトールが同時期に失踪したのは事実だ」
冗談ではないのだと肯定してしまえば『へぇ』とロキは興味を持ってしまうしかなかった。ある意味、あきらめの境地だ。
『ふたりが駆け落ち』云々は事実ではないかもしれないが、かの地でも変動は続いているらしい。
「それで、ふたりの件とキミたちのその状態って繋がりがあるのかな? それとも、それは別件?」
どうしてふたりとも、元の力量よりも力が増しているの? 存在自体が不安定になりそうなほどに。
ヘイムダルとフレイは、神でなくともさすがの眼力だな、と顔を見合わせた。
「ロキ、お前はあれからあの世界がどうなったのか知らないのだろう? 強大な『力』を抱えていたオーディン様の肉体の急激な崩壊は、小さな神界で吸収するにはあまりにも唐突だった」
「僕たちは仕方なく、飽和して爆発寸前の『力』を各自で取り込んだ」
おかげでこのありさまだ、とヘイムダルは手の平を掲げた。
神としての魂や肉体の許容量を超えた力が、魂を削り、肉体を弱らせている。小さな器に大量の水を一気に注ぎ込めば、あふれるどころか、下手をすると器自体が壊れる。
ロキの目には、ふたりの状態がとても危うく見えた。ヘイムダルが緑の陽光に透かした手は、いつ破裂してもおかしくない水風船。
北欧の神々は、ギリシャやエジプトを代表とする神界ほどには神が多くない。大神の崩御は、個人にぎりぎりの負担を強いているのだろうと容易く知れた。
場所をかえようと提案したのは、まゆらから不安定な状態に見えたふたりを引き離す意味もあったのだ。
「もちろん、僕たちも取り込んだ『力』を時間をかけて自浄消化できるまでこのままの状態でいるつもりもない。『力』を別の存在に作り変え、分散させる作業も進めている。新しい『力』の依り代となる世界樹も順調に育っているところだ」
あの時は――オーディンの肉体に宿ったバルドルとの対決の時はああするしかなかったとは言え、それでなにもかもが終わりになったわけではないのだと痛感させられる。
時はとどまることを知らず流れ続け、変転し続けているのだ。ロキの知らないところで。
「だとしたら、フレイヤとトールの不在は、キミたちにとって死活問題だってのはわかる。わかった、仕方がないから協力するよ」
もはや神ではない身でなにができるのかと自問しながらも、できるだけのことはやろうと決めた時、
「そう思うのならロキ、神界に戻って来い」
フレイの言葉を、ロキはどう取ればいいのかわからなかった。ここで冗談を言うだろうか、いつでも頓珍漢なフレイでも、いくらなんでも唐突過ぎる。
だがフレイは、やはり本気にしか見えない真面目な顔で言葉を続けるのだ。
「貴様は『神ではなくなった』とは言え、本質はなにもかわっていない。フレイたちの状態を判別できるのがその証拠だ。『ただのヒト』に神の存在が理解できるか? 『神』ではなくとも、ロキには『力』を受け入れるキャパシティがある。言うなれば、水が入っていない空っぽのプールだ。フレイが神格を与え、オーディン様の『力』を注ぎ込めばそれで神界は安定するはず」
フレイたちがここに来たのはフレイヤちゃんを探す為よりも、貴様を連れに来た方が大きいのだと言ったら――どうする?
「なにを言って……」
ロキは先から明かされ続ける神界の事情の上に乗せられたフレイの言葉に、もはや思考がフリーズ寸前だ。
なにを真面目ぶってまともに聞こえる台詞を口にしているのだろうフレイは。ぼんやりと素で失礼な考えをしてしまう。
恐る恐るヘイムダルの方へと視線をやれば、相も変らぬ仏頂面だ。
不本意ながら仕方がないとありありとあらわしているヘイムダルの仏頂面に、それがフレイの戯言ではなくふたりの合意であるのだと知って、ロキは地面へと視線を落とした。
―― 神となって、神の世界に戻る ――
ほんの一年前まではそれこそを渇望し、ほんの数ヶ月前まではそれを不思議に感じさえしていなかった。
けれども、ロキの心の中に浮かんだ単語は――『なにを今更』だ。
神であろうとなかろうとおのれはおのれなのだと気付いてしまった今となっては、どこにどんな形で存在していようと構わないし不都合も不満もない。
いや、誰かの勝手な思惑やお綺麗な自己犠牲に振り回されないだけ、今の方が自由で伸びやかで清々しくさえある。
たとえ、暑さ寒さや味覚、嗅覚、触覚、視覚、聴覚に薄い膜がかかったような、この上もなく不明瞭におのれを取り巻く世界が見えていても、それも普通の『ヒト』の感覚とかわらないのであれば問題がない。今更、明瞭で強大な『特別な神の知覚』など欲しくはなかった。
「それがイヤなら、フレイヤちゃんと馬鹿トールを探すのに必死で協力するんだな。いくらロキ と言っても今はただのヒト。このフレイが神としてカッコ良く浚って無理矢理神格を与えればすべて解決なのだから」
フレイが笑ったのが耳に聞こえた。神格を取り戻した後のロキの復讐を受ける覚悟があるのだとの含みすら込められた言葉に、拒否権はないのだとロキは悟らずにはいられない。
小さいとは言え世界のひとつに対しての責任をフレイ一人が負うと示されては、拒否権などあるわけがないではないか。神と言えど、たったひとりが負うには大きすぎる決心を見せられては、拒否できるはずがない。
「……タイムリミットは?」
フレイヤとトールを探し出す。
または、フレイとヘイムダルがこの世界に留まれる時間は。
「二日」
たったの二日。それは同時に、ロキの進退が決まる時間。
世界は不思議に満ちているものだ。退屈で仕方がなかった神界時代からは想像もつかないほどの変転に、ロキは思わず笑みを浮かべ、緑の天井を仰ぎ見た。
爆発寸前の爆弾を幾つも抱えているのだとはとても思えないほどに、この世界は綺麗だった。
この美しい世界に損害を与えない為には、二日以内に『異国の神々』をまとめて元の世界に追い返さねばならないのだと考えると、そのはちゃめちゃさにロキは面白い気分になるのであった。
***
「ホント、どんな関係なのかな、あのふたり」
出かけてしまったロキを待たず帰宅したまゆらは、自室のベッドの上に腰掛けてぼんやりと考えていた。
ロキと同じ年ほどのフレイと、ヘイムダルと名乗った子供。
フレイだけならまだ幼馴染とか学生時代の関係者と考えられなくもなかったが――ロキの『幼馴染』や『学生時代』なんぞ想像するのは大変難しかったが――ロキのヘイムダルに対する反応もフレイへのそれとたいしてかわりがないところを見ると、どうやらふたりとも同じ立場にいるようだ。
結局フレイははっきりとした回答をくれず、まゆらの疑問は宙ぶらりんのまま。
別に、周囲に知り合いらしい知り合いがいないロキを自分だけが知っている、と言う倒錯的な喜びがあるわけじゃない。むしろ、知り合いらしい知り合いの影が今までなかったロキに、親しく懐かしく言葉をかける存在があったのは喜ばしいはずなのに、なぜだか素直に喜べないのだ。
考えてみれば、ロキに『我が探偵社へようこそ!』と手を差し伸べられてから、まだ数ヶ月しか経っていない。そのほとんどは、屋敷の残骸、崩れた塀しかなかった敷地になんとか生活できる掘っ立て小屋建築に費やしたようなもので、彼の生活が落ち着いてきたのはつい最近の話だ。
毎日騒がしく忙しく過ぎて行くのに流されて、よくよく考えてみれば、ロキ個人のことなどほとんど知らないに等しかった。
いや、『今のロキ』なら少しは知っているつもりだ。
だけど、『今までのロキ』――ロキの過去や周辺事情については、何も知らない。そして、未来のことも。
彼がどこから来て、どこに行くつもりなのか、何も知らない。
「前にもこんな気持ちになったこと、ある」
探そうにも、その人のことをなにも知らなくて、探しようがなくて、途方に暮れた。
目の前からいなくなって、『良く知っている』と思い上がっていたのだと打ちのめされた。
悲しくて、泣きたくて、喪失が苦しくて、どうしようもなくて。
でも、悲しんでいても、泣いていても、苦しんでいても探さなければ二度と会えもしないから街中を歩き続けたのに。
『それがどんな意味を持つの』――その疑問から目を逸らし続けた、数日間。
またそれを味わうことになるのかもしれないと感じると胸が苦しくなって、まゆらは膝を引き寄せて小さくちぢこまる。
そして同時に思うのだ。
『そんな気持ちを誰に向けたの? そんな相手はいないのに――……』
幼い頃に死に別れた母、だろうか。でも、その時とこの気持ちは微妙に違う気がする。
まゆらは、膝を抱える手に力を込める。
ロキは一体何者なのだろう。
そして、わたしは彼にとっての何なのだろう。
何に――なれるのだろう。
そして気がついた。
ロキは時折、わたしを、とても遠くの風景を眺める視線で見る時があるのだと、気がついてしまった。
残骸だけしかない広い敷地を妙に懐かしく感じたわたしと同じ視線。
時折、蛇や黒い犬を昔から知っている気持ちになるわたしと同じ視線。
とても懐かしいものを眺める視線をどうして彼が持っているのか。
その答えもわからなくて、抱えた膝に頭を押し付ける。
そうしても、疑問や不安は消えないとわかっていても、そうせずにはいられなかった。
|
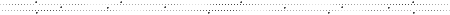 |
【 八 】
夏と言えば、秋と同じくらいに果物が豊富な時期だ。
まだ気温が上がりだす前の光に照らされた狭い掘っ立て小屋もとい燕雀探偵社は、甘い桃の香りに包まれていた。
発泡スチロールと保冷剤に守られて冷えた状態で大切に運び込まれたふたつの桃は、まゆらの手によって薄い桃色の衣を脱ぎ、白い果肉だけの姿になってガラスの器に一切れずつ盛られて行く。あとは食べられるのを待つだけの運命だ。
フェンリルは発泡スチロールが開けられた瞬間から部屋にあふれた芳しく魅力的な香りにそわそわし、今はまゆらの足元に行儀良く座って期待に満ちた目で彼女の手元を見つめ、 普段はもったいなくて奥にひっこめている『愛嬌』の武器を持ち出して振りまいていた。
時折よだれがたらりと垂れ、フェンリルはぺろりと口のまわりを舌でなめまわすが、床には 無意識のしずくがひとつふたつと点をつくっていた。
「桃って、どこか懐かしい気がしない?」
まゆらは手元の桃の薄い皮をゆっくりと剥きながら、聞くともなく質問を向けていた。
「わたしのおじいちゃんたちの家も東京だから『田舎』って感じじゃないんだけど、どうしてだか桃を見るとね、懐かしくなるの」
お母さんが好きだったからかなぁ。
まゆらは皮を剥く手をとめずに話し続けている。
「病院でお母さんに桃を剥いてもらったの、覚えてる」
フェンリルはまゆらの話など聞かず、大人しく待っているのも限界に近いのか、彼女の膝に手をついて乗りあがろうかどうしようかと迷って右の前足をうずうずと動かしていた。
舌は先から高速でべろべろとおのれの鼻を嘗め回し、尻尾はネジにでもなったように高速で左右に振られている。パタパタパタパタ、床を毛先が叩く音はとまりそうもない。
「懐かしい?」
なんとなくわかる気がする。ロキも特別桃に思い出などないが、桃の甘い香りややわらかさや繊細さは、記憶の奥底にある郷愁の念に似ている。心の中の『大切なもの』のある場所に似ている。
「ロキさんね、時々、そんな目でわたしを見てるでしょ?」
ガラスの器に一切れ入れながら、まゆらはなんてことのない話題を口にするさり気なさを装う。
指先がふるえているのは桃の果汁で指が滑ったからだと勘違いしてくれないかと少々願っているのだけれど。
「そう、かな」
指摘されたロキも、一瞬、遠い目になった。
どうしてだかまゆらは、ロキの顔が見られなかった。手元の桃と、足元のフェンリル以外は見られない。
「うん、そうかもしれない。まゆらを見ていると、とても懐かしい気持ちになるのは本当だから」
甘くやわらかく繊細で、大切なものを見ている心地になる。
「昔、大切にしていた小さな子がいてね。無邪気で、それでいて無鉄砲で、見ていて飽きなかった。今はもう、会えないけれど」
「病気かなにかで……?」
いいや、とロキは首を横に振った。
「随分と昔のことだから」
そしてまた、懐かしいものへ向ける色で、桃とまゆらを眺める。
随分と昔――たった数ヶ月前であるのに、振り返ってみれば『随分と昔』の気もする。
無邪気で無鉄砲で、見ているだけで飽きなかった小さな女の子は永遠に失われてしまった。何故なら彼女はもう、無邪気なだけの女の子ではないのだから。桃を剥く手に落とした視線に憂いをも含む女性にあざやかに変貌していた。
喪失感が彼女を成長させたのだと、大人にしたのだと考えれば、苦いような甘いような気持ちが心に湧くのだと誰にも教えるつもりはないロキである。
甘い甘いだけの時間はとうに過ぎていて、どちらももう立ち止まってはいられない。前に進むか流されるのかは、互いの選択に委ねられるのだろうけど。
「ボクのこと知りたいって、興味持った?」
まゆらの手元が、ぴたりととまった。
「そ……そんなんじゃないもん」
薄くまとった大人っぽさなど、次の瞬間には吹き飛んでいた。そこには、まだまだ子供っぽい女の子がいた。まゆらの『大人っぽさ』など、彼女が手にした桃のように、まだまだ人の手で簡単に剥けてしまえるほどに薄い。
先とは違う意味でロキの顔を見られなくなったまゆらは、沈黙を誤魔化す為にフェンリルに桃の一切れをやった。フェンリルは桃をつるりと丸呑みし、満足そうにぺろりと鼻先を舐めあげ、さっそく次の幸運を待つ為に座り直している。
「ふーん、そう? だって、今までそんなこと、聞かなかったじゃない」
「聞かなかったこと、ないもん。どうしてこんなところに住んでるの? とか、料理も満足にできないで一人暮らししようなんて今までどうやって生活してたの? とか、ちゃんと聞いたよ。ロキさん、いつもはぐらかしてばっかりだから、最近はあきらめてただけ」
桃の皮を剥く手付きとは正反対の仕草で果肉の山にぐさりとフォークを突き刺して、まゆらは器をロキへと差し出した。白い山の頂上に突き刺さったフォークは、雪山登山隊が山頂に掲げた旗のようだった。少々物騒な雰囲気で聳え立っているところが違うけれど。
「あきらめてたんだ? なんだ、ちょっとは興味持ってくれたのかと嬉しかったのに」
「…………意味わかんないデス」
ぶすりとしたまゆらの声に、フェンリルは『次の幸福』はなさそうだと悟り、パタパタと高速でしっぽをふるのをやめた。心なしか、まゆらを見上げていたキラキラおめめも輝きが半減している。
いつもの不機嫌に戻りつつあるフェンリルの顔を眺めながら、まゆらはぼんやりと考える。
――これも『興味』……なのかな? ロキさんの過去とか、今なにを考えているのかとか、気になるのは――……
でも、『興味』を持っているのだと思われるのも癪なので、顔をキッとあげロキをねめつけて
「ソレ食べ終わったら、お庭で髪切りましょう!」
まゆらはロキの次の行動を決め付けた。
「髪切りましょうって……まゆらが? ボクの?」
「だって、だいぶ長くなってるもの。前髪も時々鬱陶しそうにしてるでしょ。視力悪くなりそうだし、気になる」
行動の突拍子なさは今も昔もかわらないじゃないか。やはり人は急にはかわらないものらしい。
ロキは甘い桃を食べながら、思わず思考を飛ばしてしまう。
光太郎の依頼の先に起きた三件のプールの調査もしなければならないし、フレイヤやトールも探さなければいけないのだけれども……もちろん、有木澤家のビーグルだって探さなければならないけれども……
ぶすりとしたまま睨みつけるようにしてこちらを見つめているまゆらの視線を受けるに『忙しい』や『また今度』と口にしづらく、ロキには了承するしか選択肢はなかった。
きっとこの目が気になって、調査もなにもなくなるだろうことは軽々と予想ができたので。
段々と弱くなっているなと感じずにはいられないロキであった。
|
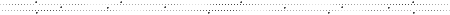 |
【 九 】
もしかしたら、まゆらは突拍子もなく『髪切ろう!』なんぞと言い出したわけではないのかもしれないと思ったのは、まゆらがカバンから取り出した髪切りバサミを見たからだった。
指示されるままに庭の日陰に椅子や新聞紙を運び出し、ロキはちょこなんとその上にいつの間にやら座らされてしまっていた。
手際よく首に巻かれた大きな布もきっとまゆらのカバンから出てきたものに違いない、探偵社内には見当たらない品物。その他にも、探偵社内にはないものが次々と彼女のカバンからは取り出され続けた。
しゃきんしゃきんとハサミの具合を確かめている音がすぐ耳元で聞こえた時、ロキははたと気がついた。
「……つかぬことを伺いますけど、まゆらさんは床屋さんでしたっけ?」
過去と現在を思い返すに、彼女は女子高生で、おしかけ探偵助手で、神社の娘であったはずだ。そこに『床屋』のスキルはないはずである。思わず口調が『おそるおそる』になってしまった。
「大丈夫大丈夫。パパの髪、わたしが切ってるから」
ほら逃げない! と後ろから首根っこをつかまれてぐいっと下を向かされては、いくらロキでも逃げられなかった。
丁寧に櫛梳られ、ハサミが最初の一切りで髪を切り落とす。もうここまできてはロキも腹をくくるしかなかったが、まゆらの手際は驚くほど良く、しゃきしゃきとハサミは進んで金色の髪を切り落としていく。
終わり! と言われた時には『もう?』と驚いたほどで、鏡を見てロキはもうひとつ驚いた。
「まゆらって、時折妙な特技持ってるね」
鏡の中には、なかなかさっぱりとした自分の顔が写っていた。こちらの態度次第で相手に天井知らずの好印象を与える見てくれだとはしっかりと自覚していたが、髪をさっぱりとさせたことで好印象はもう一段上がり、聞き取り調査もしやすくなるだろう。
鏡にはやや自慢げなまゆらの横顔も写っている。もしかしたら、このあたりもまゆらの手の平で転がされているのかもしれないと少々ぞっとしたりした。
と、その鏡の中にもうひとつ、この場にいないはずの顔を見つけてロキはぎょっとした。恨みがましいと言うか羨ましがっていると言うか、とにかく笑顔とはほど遠い顔をしたフレイがまゆらの背後にどどーんと突っ立っていたのだ。
「ロキ、羨ましいのだ。まゆらちゃんに髪を切ってもらうなど〜〜〜」
言葉は『羨ましい』だが、声色は完全に『恨みがましい』だった。
あれ? 昨日の……? まゆらは後片付けをしながら小首をかしげた。昨日フレイさんに名前を名乗っただろうか? 名乗ったような名乗らなかったような、と思いつつ、まゆらはフレイに申し出てみた。
「良かったら少し切りましょうか?」
「おぉう、まゆらちゃんが切ってくれるのなら丸坊主になってもいいのだぞぃ」
フレイはまゆらの申し出に感激しているようである。丸坊主になるほど長い時間一緒にいられれば彼にとっては本望かもしれないが、丸坊主ならバリカン使用の短時間で終了だから夢を見る暇もないはずだ。もちろん、暑いもとい熱い気持ちを訴える時間もあるはずがない。
ロキはそんなことを考えながらフレイの漫才のような反応を眺めていると、夏の陽射しに切り込むような電子音が響いた。昨日も聞いた携帯電話の着信音だ。開け放したままの掘っ立て小屋から聞こえてくる。
「ロキさん、ケータイ鳴ってるよ」
と言われても、てるてる坊主と大差ない格好で走って行くわけにはいかない。本当に、ちょっとは相手の事情を斟酌してくれと電話に愚痴りたくなる。短いとは言え切りっ放しの髪を周囲に撒き散らす結果になってしまうではないか。しかし、そもそも電話とは相手の都合を斟酌してかかってくるものではなかったので、どれだけ愚痴っても現状はかわらない。
まゆらが気がついたのだろう、ハサミを片手に探偵社へと入り、ぱたぱたと小走りで戻ってきた。彼女の手の中で青い機械仕掛けの四角い鳥は歌うことをやめず、体を小刻みに震わせ、喉を嗄らして催促している。
ディスプレイに表示された数字は光太郎のものだ。
その上部には同じように『垣ノ内光太郎』の文字が光っていた。こちらは昨日、勝手にまゆらが登録したものだ。機械オンチのロキに『電話帳登録』などできるはずもなかった。
彼からの電話はなにかと思えば、捜査の進展報告を求めるものではなく、新情報のタレこみだった。
『探偵んちの近くにある小学校のプール。同じ現象が朝一で起きたらしいぞ。今から行けば現状が見られるかもしれない』
聞いてみれば、市民プールと燕雀探偵社の中間地点にある小さな小学校が現場だった。時刻はほんの一時間ほど前としかわからない。後は現場で情報を仕入れるしかないだろう。
「ぷーるぅ? そんなことしてる場合じゃないだろうロキっ。フレイの依頼はどうするのだっ。フレイヤちゃんを探すのだっ」
聞き耳をたてていたらしいフレイが子供っぽくぷりぷりと頬を膨らませた。そこには『豊穣神』としての威厳はかけらもなかった。
確かに、重要度から言えば『神様の依頼』の方が大事だろうけれど、ロキからすれば光太郎の依頼の方が先だったのだ。こちらもないがしろにできるわけがない。探偵業とは信用第一。依頼の反故など以ての外。
「あーもう、ちゃんとわかってるよ。でも、プールの水が消えたり戻ったりってこっちの依頼も変なんだからしょうがないだろう?!」
だだっこのように手足をジタバタしかねないフレイへとため息混じりに教えてやれば、なぜかフレイはするりと真顔に戻った。
「水が消えたり戻ったり……??」
「そうなの! しかもその戻った水がすごく甘くって! 燕雀探偵社はじまって以来のまっとうなミステリー!」
まゆらが楽しそうに、または誇らしげにフレイへ情報を振り与える。そこにはもはや守秘義務もへったくれもなかった。
フレイはなにを考えているのか、つと黙り込んだ。さすがに今日は本当に『真面目』に見える。
だがフレイは真面目な顔に似合わずがっしとロキの片手をつかまえて
「そのプール、フレイも行くのだ」
フレイヤとトールとはまったく関係のなさそうな調査へと首をつっこむ宣言をし、てるてる坊主を引きずって道へ走り出した。
***
保護者やボランティアが観察員を勤めて夏の間に何回か開放される小学校のプールへとたどり着いた頃には、怪奇現象を気味悪がった大人たちが数名頭を突き合わせ、明日以降のプールの閉鎖を検討しているところであった。
元から監視員を面倒臭がっていた保護者がメンバーに多かったので、大方閉鎖は本決まり。あとはこの怪奇現象を校長や教育委員会にいつ誰が報告に行くかの押し付け合いが話しの中心であった。
彼らの話を拾い集めてみると、朝一番の開放プールの下準備の為に保護者が三人連れ立ってやって来たところ、もうすでにプールは空っぽだった。
設備の準備をし、更衣室の鍵を開け、あとは事故などがないように監視をすれば良い。その程度の説明しか受けていない保護者たちは、
「まさか、水を入れるところからやれって言うんじゃないよな」
「今までそんなのしたことないですよ」
不安げに顔を突き合わせ、もう一度プールへと戻ってみれば、プールにはなにごともなかったかのように水があった。
三人とも寝ぼけているのかと頬をはたいてみたが、水が入っている現実はかわらない。
かと言って、ほんの数分前に見た光景だって現実だった。水が入っていないのだと確かめる為にひとりがプールに降り、中心部分まで歩いたくらいなのだから。小さな水溜りだけがぽつんと残るプールの中心部に惜しげなく夏の明るい光が降りそそいでいる光景がまぼろしなのだとしたら、三人とも揃って心療内科にかかる決心をしただろう。
「ふ〜ん、となると、水がなくなっていた時間はわからないってことだな。でも、騒いでいる短時間で水がいっぱいになっていたのなら、一連の現象と同じだと見るべきかな」
ロキは腕組みしつつ、フェンスの外側からプールを眺めた。さすがに『探偵』の肩書きでは小学校のプールには入れてもらえなかった。保護者とボランティアの割合が女性に傾いていれば髪を切った効果と相まってそれも可能であったかもしれないが、夏休暇をあてているのか全員が男では手も足も出そうにない。下手をすればいらぬ反感を買って、変質者と決め付けられて警察にご報告だ。
「せめて、水を確かめられたらいいのにねぇ」
水が甘ければ間違いなく『新しい事例』になるだろうに。まゆらは心底残念そうだ。プールのフェンスから手を伸ばしても、水はひとしずくも手に入らないので確かめようもない。水が桃や蜜のように濃厚な香りを振りまいていれば、離れていてもわかるだろうに。
「さっきまゆらちゃんが、水が甘いと言っていたな。それは砂糖のように?」
「いいや、自然の水の甘み」
フレイは質問を向けたきり、やはりなにかを考えているようだ。
その彼が、反対側のフェンスのそばになにかを見つけた。
|
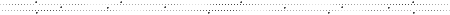 |
【 十 】
「ロキ、あそこになにか落ちてるぞ」
フレイが指差す方へ視線を向ければ、確かに薄く銀色めいたものが落ちているのが見えた。
急いで反対側へとまわり、フェンスから腕を伸ばして回収してみれば、それは銀色の鳥の羽だった。
「綺麗な羽ねぇ」
まゆらはうっとりとした視線をロキがかかげ持つ羽へと向けている。
まるで、銀細工でつくった芸術品のように美しい鳥の羽だった。夏の光に銀色の一筋までもが輝いている。
「ロキ、もしかしたらフレイヤちゃんがこの近くにいるかもしれない」
フレイだけが、銀の羽に別の意味を見出し、隠された真実を引きずり出そうとでもする目で羽を見つめた。鳥の羽を見つけてからこちら、なにやらフレイの視線が険しい気がするロキであった。
「昨日、別の生き物を作り出したと話をしただろう。フレイヤちゃんが、水を飲み乾す生き物をつくったと言っていた」
もしその『水飲み』の鳥だとしたら……?
ロキの手にある鳥の羽は、先から先まで測っても、せいぜい十センチだ。艶やかで繊細な羽は、なるほど、神の創造物に相応しいものだ。神の創造物であるならば、鳥自体の大きさが鳥が起こせる現象の大きさとは限らない。小鳥と言えど、プールいっぱいの水は軽く乾せるだろう。
「どうやら、プールの怪現象とフレイヤは繋がっているみたいだね。おそらく、トールも関係してる」
「うむ。もしかしたら、フレイヤちゃんはこの鳥の行き先に……」
そうだとしたら、市民プールの破壊痕も説明ができる。
プールの怪現象にフレイヤの創造物が関係するのならば、同時期に姿をくらませたトールも関係していると考えておかしくない。
フェンスを断ち切り、プールサイドを『残骸化』していた攻撃の痕は、トール神が振るうミョルニルの衝撃波に似ていたのだ。もうこうなればそれは『似ている』どころの話ではなく、彼の手による破壊痕だと考えて間違いがないだろう。
もしかしたら、フレイヤとトールは一緒に行動しているかもしれない。
どちらにしても、この鳥を追いかければ、フレイヤかトール、どちらか一方はつかまえられるはずだ。
フレイはロキの手から羽を取り上げて、
「フレイがなんとかするのだ」
かろやかにマントをひるがえし、小学校から消え去った。
***
今更行っても手がかりなど微塵も残ってはいないだろう小学校二件と中学校一件におもむき、案の定一言の証言どころか事実確認すらできなかった。
開放プールを楽しんだ小学生の一群に話を聞こうにも、最近の小学生に噂話程度の情報でももらえないかと声をかけようとしても、周囲の大人のガードが固すぎて近づけもしない。この時ばかりは、数ヶ月前のおのれの状態であれば……と思わないでもない瞬間であった。
せめてまゆらを連れてくるべきだったか、彼女であれば小学生からも難なく情報を得られただろうに、とそこまで考えて、案外と彼女をあてにしているのだと再確認させられる。いいや、もう十分におんぶにだっこ状態なのだから、これ以上は沽券に関わる。頑張っていこう。
とは思いながらも、結局、『先の三件には破壊痕はなかった』以外の確認はとれずに夕方まで時間を浪費し、落ち込みながら探偵社に帰ってきたロキを出迎えたのは――なんと朝方別れたフレイであった。
まゆらもいないのだろう、彼は軒先に置いた足踏み台代わりのビール瓶ケースをひっくり返して座っていた。
無駄に豪奢な盛装と黄色のケースはこの上もなくミスマッチのはずなのだが、フレイが座るとさまになっている気がするのはなぜだろうか。背筋を伸ばし、黙って立っていれば『王子様』と言っても通用するはずの――いや、実際身分は『王子様』であるのだが――品の良い見てくれであるはずなのに。
もしかしたら、彼がむしゃむしゃとほおばっている、夏の野菜であるトウモロコシのせいかもしれない。焼きトウモロコシにさっとひと刷けされたのだろうしょう油の香ばしい匂いが、王子様を庶民に引きずり下ろしていた。
足元にはどこから取り出したのか、蚊取り豚の口から蚊取り線香の煙が夕方の空にゆるく煙っている。ここまでくれば、もはや完全に一般庶民である。
と思えば、それは先日まゆらが持ち込んだ白黒ブチの蚊取り豚だった。
『可愛いでしょ、ぶちぶちの蚊取り豚!』
……たしかにそんじょそこらでは見かけないブチ蚊取り豚だと妙に感心した記憶が思わずよみがえる。王子様を完全一般庶民にしたのはまゆらだったのか。
いや、そもそも、その焼きトウモロコシも彼女の手製ではないのか。昨日の昼にたんまりともらった家庭菜園の収穫物のひとつ。
「……まゆらは?」
「麗しのまゆらちゃんは、甲斐甲斐しくも真っ黒い息子のお散歩なのだ。フレイもついて行きたかったが、今はフレイヤちゃんの方が先なのだぞぃ」
むぅぅ、本当に残念なのだーっ! とトウモロコシとは反対側の手をくやしそうににぎりしめたフレイの肩には、鉄くずで作成したような鳥の模型がちょこなんととまっていた。そこらに転がっていた廃材でできているようにしか見えなかったが、黒いつぶらな瞳などはなかなかに愛嬌があるし、細身のフォルムや喉から胸元にかけてのラインは美しかった。
「これかい?」
鳥からは、かすかに朝方フレイが持ち去った銀色の鳥の羽の気配がする。いつもなにやら妙ちくりんな発明にいそしんでいる彼のこと、たった数時間で探索機をつくるなど簡単だろう。
もしゃもしゃと残りのトウモロコシを咀嚼しているフレイの肩にとまった鳥へと指を近づけてみれば、ソレはがぶりとロキの指を噛んだ。
「…………フレイ、なにか恨みでもあるのかい?」
鳥はすっぽんよろしく、ぎゅむむむっとくちばしを上下にあわせたまま開こうとしない。小さな鳥であるのに、押しても引いてもくちばしは動かない。痛くもかゆくもないが、鬱陶しくはある。
「ヒトでも神でも鳥でもツクリモノでも、断りもなしに触られて気分良いわけがあるかいな」
フレイは食べ終わったトウモロコシをぽいっと敷地内に生えているハナミズキの根元に放り投げた。
ヒトでも神でも鳥でもツクリモノでももちろん木でも、ゴミをそのへんに捨てられて気分が良いはずがない。ロキは残っている方の手ですっぱんっとフレイの後ろ頭をはたいてやった。
そのはずみで鳥はくちばしをぱかりと開き、ついでにスイッチが入ったかのように羽ばたき始め、夕方の色に染まりかけた空をくるくると飛び回った。
そして、なにかを発見したのか、いきなり両目がピカッと赤く光り、それからピカピカと点滅させたまま探偵社の敷地内から出て行ってしまった。
「ロキ、どうやらあの羽の本体を発見したらしいぞ」
フレイはさっとマントをひるがえして鳥の後を追い始め、ロキもフレイの後を追いかけた。
後には、誰も拾ってくれないトウモロコシの残骸が屋敷の残骸に同化しているばかりであった。
時を同じくして、ロキとフレイが走り去っていった方向と反対側から探偵社へと近づいてくる影がある。黒い犬と、髪の長い少女だ。
主であるロキのかわりにおしかけ探偵助手のまゆらにたっぷりと散歩をさせてもらった――彼の視点から見れば『散歩をさせてやった』である――フェンリルはご満悦の様子で、歩くたびにしっぽをふりふり、お尻をふりふりしている。
あとはたっぷりと夕食を用意させ、冷たい水を好きなだけ飲んで、夜の涼しさを堪能しつつ優雅に寝る予定だ。『忙殺』の言葉を知る人間からするとなんとも羨ましい一日である。
フェンリルはその平和な一日がつつがなく過ぎるのだと信じて疑わない歩調で塀だけは無駄に長い敷地横の道を通り、鉄門跡を曲がって掘っ立て小屋へと向かいかけたのだが――その掘っ立て小屋の前に、人間がひとり突っ立っているのを見つけて足をとめた。
人間は、今にも崩れ落ちそうな探偵社の屋根を眺めていた。
優秀な燕雀探偵社の守護者を自認しているフェンリルは『わんっ!』と威厳たっぷりに威嚇した。
威嚇にびくりと肩を震わせて振り向いたのは、眼鏡をかけた、まだ若い女性だった。おどおどとした顔をしているがどろぼうが常に自信たっぷりであるわけがない、どろぼうを驚かせたのだとフェンリルは内心ご満悦だ。
だからもって、おのれのリードを持ったまゆらの反応は予想外だった。
「関屋さん?」
「あぁ、大堂寺さんちの! よかったぁぁぁぁっ!」
「??」
どろぼう、もとい関屋と呼ばれた女は、いきなりまゆらにがっしと抱きついた。
どろぼうじゃなくて変質者なのか?! フェンリルはどうしたらいいのかわからずに、ふたりの足元でかたまってしまった。変質者への対策なんぞ一度たりとも考えたことがない。
夕方の空に関屋の安堵の声だけが不自然に響き渡った。
|
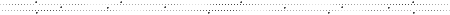 |
【 十一 】
東から少しずつ夜の色が忍び寄る空に、神の創造物の鳥が飛ぶ。
鳥を追いかけるのは、ふたりの男。
片方は神、もう片方は元・神。
「どこに行く気だろう」
まっすぐに飛べば信憑性もあるだろうに、造物主に似ているのか、鉄色の鳥はあっちにふらふら、こっちにふらふらとしてふたりを惑わせていた。空の上では袋小路なんぞ関係ないであろうが、鳥の気まぐれによって何度も行きつ戻りつをさせられては、行き先を問いたくもなるだろう。
「フレイの発明にケチをつけるつもりか?!」
うぬぬぅ、ロキのくにせっ。フレイはよくわからない理由でくやしげに歯噛みしているが、造物主であるフレイも疑わしそうに鳥を見上げているのに気がつかないロキではなかった。
「あ、目の点滅がとまったぞぃ」
指差されてみれば、ピカピカと不気味に点滅していた目が、今度は青色に光っていた。そして今度は、先までの迷走が嘘のように、まっすぐに飛んで行く。
「あっちの方向には、たしか……」
あちらこちらに散々振り回されて位置感覚が狂っていなければ、あちらの方向には、たしか――……
「公園が」
そこには、ボートを浮かべられるほどに大きな池が作られている。
ふたりは公園めざして走り続けた。
***
小高い丘のすそに作られた広い公園には、丘をも含めた遊歩道やアスレチック遊具、芝生が綺麗に敷き詰められた広場などがある。
敷地の半分近くを占めているのは、人工の池だった。ひょうたん型と言うよりは茄子の形に近いいびつな楕円の池には、休日ともなると色とりどりのボートが浮かべられ、若いカップルや友達同士やはたまた親子連れが櫂を手に船遊びを楽しんでいるものだ。
だが、夕方ともなればさすがに夏休みであっても営業時間は終了なのだろう、ボートはすべて回収され、池の脇に建てられた小屋の前に行儀良く並んでいるばかりで、人の影すらない。
そんな場所に、若いカップルがいた。
ひとりは、木刀を手にした黒髪の少年。もうひとりは、彼よりかは幾分年上の、金色の髪を持つ際立って美しい女だった。
こんな時間に男女ふたりでいるのならばそれ相応の間柄なのだろうと考えるのが普通であったが、ふたりの間には甘い色など微塵も漂ってはいなかった。それどころか、ふたりに『カップル?』と問いかければ即行で否定しあい、お互い吐き気を催すだろう。それほどに彼らは『カップルのメッカ』とも言われるその池のほとりに相応しくない組み合わせだった。
彼らの前にあるのは、池とボートと夕方の空だけではなかった。池の中ほどの空を小さく旋回している銀色の小鳥。そして、彼らから見て少々高い地形になっている左岸にいる――茶色い垂れ耳の犬。
犬が大好きなおもちゃに向ける甘えた声で『きゅわんっ』と吼えると一瞬鳥が刻む輪が大きく乱れるが、それもすぐに持ち直す。しかし、徐々に犬から離れた空へと動いているのだと気付かないふたりではなった。
「ようやく追いついたわ。今度こそ捕まえるのよ、下僕!」
「オレは下僕じゃないっつーの!」
女の理不尽な命令に、少年は悪態をつきながらも木刀を構えた。大上段に構えた木刀を鳥に向けて振り下ろす。彼の木刀はただの木刀ではない。どれだけ距離が離れていようと、衝撃波で鳥の一羽や二羽、落とすのはたやすい。
「唸れ、ミョルニ……」
「こんっのバカ! 今度は池を壊すつもりッ!!」
女は形の良い足を高々と上げ、ハイヒールの硬い踵を突き刺す勢いで少年の後頭部に蹴りを入れた。ガツッと良い音と感触がして、少年は口からぶくぶくと泡を吹いて倒れ伏してしまった。
「あぁ! 下僕が気絶しちゃったじゃない! 誰のせいよ?」
自分のせいだとは口が裂けても言うわけがない、天上天下唯我独尊を身上とする女であった。
「あぁんもうっどうしましょう。バカトールのかわりにわたしがつかまえるしかないのかしらん」
足元で脳震盪を起こして倒れている少年の哀れな姿などアウトオブ眼中状態の女は心底困った。
さすがに愛と美の女神と褒め称えられていてもあそこまで飛べないし……あぁ誰かこないかしら?!
女が助けを求めて左右に視線をやった時――
「フレイヤ?!」
池を囲った林を抜けて、若い男の声が、女の名を呼んだ。
「――ロキ?」
女は、喜びに顔を輝かせ、男の名を呼んだ。
鉄色に光る鳥が導いたのは、やはり公園にある大きな池だった。
そこには銀色の輪を描く鳥と、茶色い垂れ耳の犬と、金色の髪の女と、倒れ伏している少年の姿が。
ロキにはふたりが、探し人である北欧神フレイヤとトールであるのだとすぐに知れた。
そして、池の上で旋回を続ける銀色の鳥は、やはり神の創造物である、プールの水を乾した犯人であるとわかった。神の光臨時期と怪奇現象の勃発時期が一緒で、目の前の光景を見るに、もはや関係がないとは誰にも言えないだろう。
ならばあそこにいる犬は? と視線をやると……
「キャスリン!」
二丁目の有木澤キャスリンがそこにいた。雷に怯えて脱走した、人懐っこい表情が特徴的な垂れ耳ビーグル。
だが、キャスリンはその名前が嫌いなのか、遠めでも人懐っこそうであった顔が変貌したかと思うと
ギャワワンッ!!
歯茎がむき出しになるほどに口を歪ませて鋭く尖った白い牙を剥き、恐ろしい声で威嚇をした。
ロキ、フレイ、フレイヤですら一瞬身をすくませたほどに恐ろしい威嚇に、冷静でいられなかったのは銀の鳥だ。
ばたばたと羽を不器用に震わせ、くるくると錐揉みしながら――池に墜落してしまった。
「わたしの鳥が! お兄様、今こそ出番ですわよ!」
こんな時ばかり都合よくフレイヤに存在を思い出される兄は、それでも喜色満面でマント姿のまま池に入り鳥を回収しようとしたのだが――……
ゴブ……ッ
不穏な音がしたかと思うと、鳥が落ちたあたりの水面が奇妙にさざなみだし……
巨大な風呂の栓を抜いたかのようにぎゅるりと渦を巻き水位が減り始めた。
フレイは渦に巻き込まれ慌てて足を抜く。渦はフレイの足先を掠めた。
「水を乾しているんだわ!」
一体どれだけの水を乾せるのだと驚嘆せずにはいられない。あっと言う間に池は十センチ、二十センチと水位を減らしている。さすが神の創造物と感心せずにはいられない。
池がすっかりと干上がればそれもそれでよし、乾した瞬間に鳥を回収すればいいかとフレイヤが考えた時、順調に減り続けていた水がぴたりととまり渦が掻き消えた。水面は一瞬鏡のようにまっ平らになったが、次の瞬間には先とは比べ物にならないスピードで水位を増し始めた。
いや、増しているどころの話ではない。恐ろしい勢いで逆流している、としか表現できない勢いで水は放出され、とうとう池からあふれ、三人の足先まで到達した。足首からふくらはぎ、膝まで到達するのではないか。いや、街中水に沈めるのではないかと心配になるほど、放水の勢いは減じることを知らない。
ロープで岸に繋がれているボートは荒く上下左右に振られ、岸へと乗り上げようとしている。
それほどまでの水難状態であるのに、地面にうつ伏せに倒れているトールを誰も心配しないところが、それぞれに唯我独尊の神と元・神である。
かすかに意識を取り戻していたらしいトールが『がぼがぼ ごぼごぼ』と意味不明の音を発しつつ伸ばした手になど、もちろん誰も気がつかない。
薄情にもトールは気にしてはいなかったが、左岸にいるビーグルは気にしていたロキは、素早く視線を転じた。なにせ、まだきちんと確認はとれていないが、有木澤宅のキャスリンだった場合、依頼を受けているのだから怪我はもちろん溺死させるわけにはいかない。かと言って逃げられてしまうのも問題外だ。
そう考えていると、犬の後にある林から誰かが近寄ってくるのが見えた。フレイがもう一羽作成していたのだろう、鉄色の鳥に導かれたヘイムダルがあらわれて、膨大な水に腰を抜かしたのか、動けずにきゅぅんきゅぅんと悲しげに鼻を鳴らしているキャスリンを保護していた。
いつもいつも邪魔ばかりしている印象の強いヘイムダルであるが、たまには協力してくれるのかと嬉しくなった。だがよくよく考えてみれば、ヘイムダルは怪現象と無関係の動物を救出しただけにすぎないのだとすぐに気がついた。なにせ彼は、有木澤の依頼を知らないのだから。
ごぉぉぉぉぉぉ……
水は不吉な音を立てて唸り続けている。
水はあっと言う間に足首まで水位をあげ、足をさらうほどの勢いで放射状に放出され続けた。
|
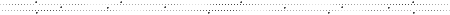 |
【 十二 】
「一体どれだけ水を飲み込んだんだ?!」
いや、そもそも『飲み乾した水』だけが鳥の内側からあふれているのではないかもしれない。なにせ神の創造物、内側の空間で水が増殖していてもおかしくない。
悠長に奔流がとまるまで待っているわけにはどうやらいかないようだ。
「お兄様、なんとかしてよ!」
こんな時ばかりは妹に盛大に頼りにされるフレイも、さすがにうなるしかなかった。
「あの鳥は水を飲むだけ? 今までプールの水がなくなってたけど、全部元に戻ってた。あれもこの鳥の仕業?」
気を抜けば足元を崩され、林に叩きつけられてしまうだろう。言葉は自然と力のこもった大声になっていく。
「ロキ、違うわ。あの子は水――『湛えられたもの』を乾すだけなの。プールの水を戻していたのは、水生み鳥」
ほら、あの子よ!
フレイヤが指差した方向には、枝にとまった小鳥が一羽。夜へと支配権が徐々に移りつつある空の中でもはっきりとわかる透明な琥珀色の翼をたたんで神々を見おろしていた。鳥は神々の困難など知らぬげな顔をして、優雅にさえずっている。唯我独尊のフレイヤが作り出したに相応しい我が道の行きっぷりであった。
「水生み鳥は水乾し鳥の抑制には――」
「ならないわ。あの子は、こちらに来てから作った子だから」
プールの水がなくなる。その怪現象を、人間たちにひどく騒がれないようにと作った水生み鳥にそれ以上の力があるとすれば、水乾し鳥の居場所を察知できる能力くらいらしい。
「うーむ、どうする、ロキ」
フレイさんはもうさっぱりお手上げなのだ。
フレイはご丁寧にも両手を挙げて見せた。まがりなりにも神であるのに、なんともあきらめがはやすぎる。
水はフレイの降参を受けて喜んでいるのか、ますます勢いをあげているようにしか感じられなかった。
その時、
「あぁっ! ロキじゃねーか!」
とっくの昔に奔流に流され、林の中へと運ばれていたトールが、木刀を支えにして三人の後ろにあらわれた。
「なにやってんだよ、お前がいるんだったらさっさとコレなんとかしろよ!」
久々の再会だと言うのに名前を呼んだ次が命令もとい他力本願なのだから、トールも素っ頓狂な男である。
「って言うか、キミたち、神様なんだからそっちがなんとかしてくれない? こちとら特殊技能のない人間なんだからっ」
特殊技能と言えば、大概の言語の読み書きができる、それくらいしかロキには残っていなかった。それも、神の特権が残ったのではなく、知識としてきちんと消化できていた為に残った『能力』だ。
「特殊技能……神……そうか! よし、ロキ、行け!」
フレイはなにかを閃いたらしいが、指をびしっと暴走する水のただ中に向けただけであった。
「だから無理だって言ってるだろう?!」
あぁもうこれだからフレイは!! 思わずロキは頭を抱えてしゃがみたくなってしまった。
「ただの人間があそこに行くより神であるキミたちが行く方がなんぼかマシだと言ったばかりだろう!」
「ロキこそフレイの話を聞いてないのではないのか?! ロキは『空っぽのプールで『力』を受け入れるキャパシティはかわらない』と」
あふれ続ける『力』を飲むのは鳥よりもお前の方が得意のはず――。
「ボクが……?」
疲労も老いも知るこの地球上にあふれる当たり前の人間でしかなくなった、このボクが?!
「そうとわかればオレが援護するぜ!」
トールが木刀を構え、池に向かって振り下ろした。衝撃波が水を割り、ロキへと道をつくった。まるで、モーゼの十戒だ。
仕方ない! ロキはバタバタと羽をばたつかせて池の底を逃げようとしている鳥へと向けて走り出した。そして、鳥を掬い上げる。銀色の鳥はロキの手の中にすっぽりとおさまるほどに小さく――そして、震えていた。
水はミョルニルの衝撃をみるみる吸収して道を飲み込んだ。
「ロキは……?!」
水の奔流がおさまり、足元が水浸しの状態になり、一面が大きな鏡になり空に瞬きはじめた星を映すほどの時間が過ぎても、ロキは姿をあらわさなかった。
***
ロキは池の水の中で、銀色の鳥を抱きしめていた。
硬質な輝きを放っている銀の鳥は冷たい印象を与えていたが、鳥はほのかにあたたかく、そして心細げに震えている。
水はどんどんと鳥の中からあふれ続けていた。ただ今までと違うのは、あふれた先からどんどんとロキの中へと流れ込んでいく点だ。
水を受けとめながらも、ロキですらその水がおのれのどこにいくのかわからなかった。
空っぽのプール。
プールは『どこに水が注がれている』と認識しはしない。ただ受けとめ、貯め続けるだけだ。
だが認識はしなくとも、容量の存在するプールであるのならばいつかは限度を超える。それは絶対的な理だ。そうであるならば、ロキが受けとめた分もいつかはあふれだすだろう。
どこまでこの鳥は水を吐き出すのだろう。
鳥の保水量とこちらの許容量の差はどれくらいだろう……
許容量が足りなかった場合、どうなるだろう……あふれてしまうだけならまだましだ。もしかしたら器ごと壊れてしまう……
そんなことをぼんやりと考えながらも、ロキはなぜか穏やかな気持ちだった。
空っぽだったところが満たされるのは気持ちがよい。たとえ、そこに注ぎ込まれているのが『力』ではなく『水』であったとしても、大きくあいた穴が埋まるのは気持ちが良い……
心が安定する。体の、魂の『穴』は本来埋まっているのが当たり前の姿なのだと思い知らされる。
この気持ちよさを、快感を、安定感を得られるのなら、『力』を受け入れ『神』に戻るのも悪くない――……
こぽり。
どことも知れない場所に注ぎ込まれた水が騒いだ。
こぽり。
もうひとつ騒いだ。
心の中に浮かんだ景色があった。
海だ。
地球の七割を占める巨大な水がめ。
自転車のペダルを踏む、セーラー服の女の子。
彼女が切る風に舞う亜麻色の長い髪が頬をくすぐるのが、実は、言葉にしなかったけれどくすぐったかった。
「ロキ君、海!」
もういい年だろうに、彼女は青い海にはしゃいだ。
夏の陽光きらめくとは言い難かったが、海も空も美しかった。夏にはまだ遠い風も気持ちが良かった。
彼女が砂で作った城。それを壊したのはわざと。
彼女の色々な表情が見てみたくて――覚えておきたくて。
怒るかと思えば拗ねるのだから、彼女らしいとちょっと思った。
拗ねていたかと思えば、みるみる表情は掻き曇っていくのだけれど。
「ねぇロキ君、鳴神君て知ってる? ロキ君は知ってるよね?」
不安そうな声。今はそんな声は聞きたくないのに。
でも、笑ってくれるような会話の糸口も見つけられなくて――少しばかり悔しい。
『神様』って言われていても女の子ひとり笑わせられないのは不甲斐ない。
「でもおかしいの、クラスの皆、誰も覚えてないの。わたしも本当に『鳴神君』って人がいたのかどうか、自分でも自信がなくなっちゃうの……」
まゆらはそんな風に、ボクのことも忘れていくんだ。
それが自然なんだ。けして重なってはいけない道なのだから。
神様と人が同じ道を歩けるはずがないんだ。ちっぽけな力しか持たない小さな存在でも、神様と人は別の道を歩く生き物だとちゃんとわかってる。
「ロキ君はさ。わたしと出会って事件解決してくれた時のこと覚えてる?」
あの事件から過ごした時間は、重なった時間ではなくて――交差しただけに過ぎない時間だとわかっているんだ。
ほんの一瞬、道が交わっただけなのだと――理解できているのに。
この空間が大切だと感じはじめたのはいつからだったのだろう。なにが原因だったのだろう。分岐点は――どこにあったのだろう。
心変わりしたのがいつなのか、原因がなにだったのか、分岐点がどこだったのかわかったとしても、そこに戻ってやり直したいとは思わないけれど。
「あの時思ったんだよ。ロキ君だったら、どんなことだって当たり前の当然のようにわたしの望みを叶えてくれるんじゃないかって」
ワクワクさせてくれて、ドキドキさせてくれて。
それでいて――『ただいま』って――安心して言える場所にいてくれるんじゃないかなって――ずっと思ってるんだよ。
「ロキ君は、まるで、わたしの――……」
「まゆら、帰ろう」
帰れたらいいね。
『ただいま』『お帰り』って言える場所に、帰れたらいいね。
帰りたいね。
一緒に歩いて行ける場所に。
キミが望んだ場所を、
あの時は選べなかったボクが、
いまさら願ってもいいのなら。
心変わりしたのがいつなのか、原因がなにだったのか、分岐点がどこだったのかわかったとしても、そこに戻ってやり直したいとは思わないけれど。
彼女の最後の言葉を聴かなかったフリをしたあの瞬間に戻れるとしたら……迷わずに。
ボク自身が選んだ道の先へと進んで――生きたい。
|
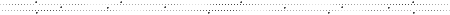 |
【エピローグ】
「そもそもの原因がなにかと言えば、全部! ロキが不甲斐ないのがいけないのよッ!」
池の底から這い出るようにして生還したロキの素朴な問いに答えたのはフレイヤだった。
どうにもこうにも、問いを口にして激昂されるとは思わなかったロキは、銀色の鳥をつかまえたまま目を点にするしかなかった。
遠く離れた、次元すら違う場所にいるフレイヤとおのれが、どうしてこの騒動の原因になれるのだろう??
空にはすでに星がまたたき、すっかりと夜の様子になっていた。それだけの時間の経過も、もしかしたら彼女を怒らせているのかもしれない。
なにせ、やっとの想いで池から――それも、カナヅチだと知っていながら誰も手を貸そうとはしてくれなかったので、まさしく『必死』で岸までたどり着いたのに、安堵されるよりも先に『遅い!』とどなりつけられたくらいであるのだし。
それから彼女はずっと怒り続けている。
「水鏡でこちらの様子を見ていれば、ロキったらちっとも! 進展もなにもないんだものっ。見ててじれったいたらありゃしないわ!」
いやあのねフレイヤ、だからなにを見て怒っているのかこちらからするともうさっぱりなんだけど。
ロキは完全お手上げ状態で、フレイヤの言われない怒りを黙って受けるしかなかった。全身ぐっしょりの、しぼればどこからでも水がしたたる体に容赦なく熱をはらんだ怒りが突き刺さる。
いや、彼女の言葉の隙間になにかを挟むなどできるはずがない、十倍返しで罵倒されるに決まっている。そう思わせるフレイヤの勢いだった。
「せっかくこのわたしが身をひいたってのに、ロキったらオママゴトみたいな生活してふわふわふわふわしちゃってっ!」
あきらめたわたしがバカみたいっ。
フレイヤはそれだけ言い切ってしまうと、今度は恐ろしいほどに黙りこくった。ぎゅっと唇を引き結び、じっとりとした目で睨みつけている。けっして言いたいことを言い切って怒りがおさまったわけではないとどれだけ鈍感な性格でもわかるだろうほどに、彼女はまだ怒っていた。
「……もしかして、フレイヤが『見てた』って……」
皆まで言うな、とトールがあきれたようなバツが悪いような、なにごとにも単純な彼にしては珍しく複雑な顔をしていた。
「フレイヤはともかく、面白半分で水鏡一緒に覗いてたオレが言うのもなんだけどさ、コレは事故なんだよ。ちゃんとふたりで解決しようとしてたトコからもわかるだろ? ふたりでこっちの世界に来て、何度も鳥をつかまえようとしてたんだ」
時空を、世界を、空間を繋げて『人間界』を映していた水の鏡に水乾し鳥が逃げ込んだのは正真正銘の事故なのだ。
こちらの世界に鳥が落ちた時、偶然にもこの世界は大嵐で、ひどい雷に怯えて水乾し鳥が慌てふためいて逃げ、その様子を見ていたどこかの飼い犬が興奮して逃げてしまったのも正真正銘事故なのだ。
ちょっと勢いが過ぎて――なにせ、オーディンの完全な『死』によって放出された『力』に馴染まないうちに『神の御技』を使った為に予想外のプール破壊行動をしてしまったのも、正真正銘の事故なのだ。
そう言われてしまえばもうなにも言えなくなってしまったロキは、あろうことか、声をたてて笑った。キャスリン脱走の理由までが、まさか彼らにあるとは予想をしていなかったこともあるけれど。
「そうだとしても、黙っていなくなるなんて不謹慎だ。あの世界が今どんな状態なのかわかってるだろう?」
ヘイムダルは相変わらず四角四面の表情と考え方でふたりに説教し、
「フレイヤちゃん、お兄ちゃんも頼って欲しいのだ〜〜」
……フレイはとことんと妹バカだった。
彼らは相変わらずで、なにも変わりはしていないのだと、安心した。
そして、遠く離れていても、気にしたり心配していてくれているのだと――『誰かの気持ち』がわかって、嬉しかった。
同じ種族ではなくなったのに、かわらず気持ちを寄せていてくれるのが、ありがたかった。
ロキの気持ちに同調するかのように、ビーグルのキャスリンが明るい声でほえてしっぽをぶんぶんと振り立てた。
ロキの腕の中の銀の鳥はもうキャスリンにほえられても大丈夫なのか、それどころか高い声で二重奏すら聞かせてくれた。
フレイヤの肩に舞い降りた琥珀の鳥も喉を震わせ、三重奏となった音楽は夜の空に高らかに響き渡っていく。
『燕雀探偵社』が抱えていた事件は、そうして、すべて無事に解決した。
***
オママゴトみたいな世界。
ふわふわふわふわした世界。
神の日常からしたら、まさしくここはそうだろう。
本の中のおとぎ話よりもまだ遠い物語。
それでもここは現実で、なによりも大切な場所。
この世界を『偽り』にしていたのは、他者ではなく自分自身。
もうこれからは誰に後ろ指指されようと、この世界こそが『真実』だと胸を張って言おう。
この世界を選んだのは、まぎれもなくおのれなのだから。
すっかりと夜の色に染まった空には、都会にしては珍しく星がいくつもまたたいていた。
街灯が等間隔で設置されていたが、ロキの足元を照らすようでもあった。
道々にこぼれているのは、人の家に灯ったあたたかい光。
その灯りをひとつずつ踏みながら、ロキは燕雀探偵社へと向かう。
すっかりびしょ濡れであったのも夜の風にさらされて九割がた乾いてきたが、今はそれとは別の意味で心底『家』が懐かしい。
おのれの『現実的な生活の場』に戻りたかった。
敷地だけは無駄に広く、崩れた塀添いに進んでもなかなか鉄門には辿り着かない。
塀が高いので家の様子は道からはわからなかったが、今はフェンリルとヨルムンガンドしかいないので真っ暗な闇に沈んでいるだろう。
そう思っていたのに、鉄門跡から見える光景は――やわらかいオレンジ色の明かりが灯った我が家だった。
夜の風を取り込む為に大きく開け放たれた窓、網戸の隙間から光がほろほろとこぼれている。
「……まゆら?」
建て付けの悪い引き戸を恐る恐る開けてみれば、そこにはまゆらがいた。
普段なら、もう家に帰っているはずなのに……どうして。
もしかして、願いが通じたのだろうか。
もしかして、声が届いたのだろうか。
『会いたかった』――その願いが、声が届いて、彼女はここにいるのだろうか。
まぼろしではないのだろうか。
「ロキさん、お帰りなさい」
耳に届いた声は幻聴ではないのだろうか。
「どうしたの? なにか顔についてるかな?」
まゆらはぺたぺたと自分の顔を心配そうな仕草で探った。彼女の行動がおのれの驚いた表情にあるのだとわかりながらも、それでもまだ信じられなかった。
一歩、家に踏み込んでも、まぼろしは消えない。
もう一歩、進めても、まゆらは逃げない。
『どうしてなのだろう』――そう考える心の反対側で、もう理由などどうでもいい気がしてきた。
まぼろしでも現実でも、目の前の光景こそ真実。
触れてみればいいじゃないか、嘘もまやかしも現実も、触れられなければ意味がないのだから。
「まゆら、抱きしめても……いい?」
あまりにもあんまりな唐突な『お願い』に、まゆらはうろうろと視線をさ迷わせ、あーとかうーとかうなっていたが、その顔は薄い桃の色に染まっていて。彼女が剥いてくれた甘い甘い桃。その香りを思い出してしまう。
「ロキさん、唐突だよぉ」
心底困った声だったけれど、拒絶の言葉ではなかったのに妙に安堵して腕を伸ばしかけたのだけれども――
「関屋さんからの伝言、聞いてからの方がいいと思うけど」
妙にひっかかる言葉で見えない壁が作られて、がっしりとガードされてしまった。
「関屋さん?」
はて、なにやらとても重要なことを忘れている気がしてきたぞ……目の前の光景よりも重要なことなんかあるか、と言い切ってしまいたい気持ちを押さえ込むほどに、重要なこと。
「翻訳の締め切りが変更になって、明日のお昼になったんだって。関屋さん、泣きそうだったよ」
「ほんやく……」
ちょっと待て、確かあと四日は時間があったはず。
と言うか、ここ数日ちっとも進んでいない。
それどころか綺麗さっぱり頭の中から抜け落ちていた。
「簡単な英語だったらわたしも手伝えるかもしれないんだけど……スワヒリ語じゃねぇ」
ロキは頭を抱えたくなった。さすがに『神の特殊技能』――言語に精通していても、個人の手紙ならまだしも会社の書類となると専門用語が花盛り。要領の良いロキでも明日の昼までに仕上げる自信はまったくなかった。
とは言っても、翻訳業も信用第一。『締め切りが前倒しになったから出来ません』なんぞ言えるわけがない。そして『勝手に締め切りを変更するな』なんぞとはもっと言えない。
翻訳のツテを失うのは、ロキ一家の死活問題に等しかった。この夏をなんとか乗り越えられても、日本には寒風吹きすさぶ冬があるのだ。冬までにあちらこちら補修工事をしないと、さすがに全員凍死する。
『あの四人、戻って来い! タイムリミットぎりぎりまでこっちの世界で遊び倒すとか言ってたくらいなら、ここに来て手伝え!』
ロキの心底からの願いを代弁しているつもりなのか、フェンリルが高く長く遠吠えをした。
空は神々を祝福するかのように夏の星座をきらめかせている。
この空の下で、少女は秋になれば桃のかわりに柿を剥き、赤く色付いたほおずきに豆電球をいれ、その光の具合に喜ぶだろう。
青年は相変わらず犬猫探しの依頼と翻訳の仕事に追われるだろう。もしかしたら時折は『不思議現象』に巻き込まれているかもしれない。
それでも世界はどこまでも美しく、彼らをかわらない優しさで包み込むのだろう。
頭上に広がる星空のように。
おわり
|
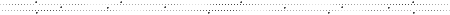
幸せ家族の、なんてことないお話でした。
|